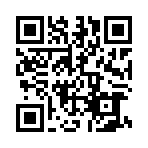八王子テレメディア・プロデューサーの巻
2010年09月23日
八王子テレメディア
遠藤さん(プロデューサー)
2010年8月16日
昨年度お世話になり、今年度も八王子未来学の
テレビ番組制作をお願いすることになった
八王子テレメディアの遠藤さんに、
プロデューサーの仕事などについて、伺いに行きました。
(写真は昨年度の撮影風景です)
――プロデューサーという仕事は何をするんですか?
遠藤さん「基本は、外部に企画を提案することです。
持ち込み企画も含めて、そういう「動き」をすばやくキャッチして、
ニーズ、予算、納期を合わせてコンセプトとしてまとめる。
しかもなるほど、という形にして話をまとめるのが大切です」
――ディレクターと呼ばれる人と、どう違うんですか?
遠藤さん「固まったコンセプトをもとに、実際に進めるのがディレクターです。
ディレクターが決まると、今度はそのディレクターと二人で、
実際にどんな番組にするかを考え、それまでの骨格に肉付けしていきます」
(詳しい内容や番組作りのプロセスは、後日インタビュー記事でお届けします)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
中学生のためのカメラ教室の巻
2010年09月22日
城山中学校
鈴木くん、城定くん、佐々木くん、鈴木校長先生、
千種さん(東京工科大学准教授)、大島哲二さん(カメラマン)
2010年7月16日
八王子事典(仮)に載せる記事を、中学生に取材してもらうために、
工科大の千種先生に、城山中学に乗り込んで、
「取材スクール」を開いていただきました。
心配そうに見ている鈴木校長先生、
そして写真には写っていませんが副校長や理科の先生に
生徒を集めていただきました。
千種先生が呼んだ、プロのカメラマンの大島さんも登場、
「目から鱗」の授業が行われたのであります。
中学生も含めて皆さんお忙しい中、大変だったはすですが、
内容はすばらしいものでした。
たとえば、下の写真2枚は、同じ段ボール箱を撮ったものですが、
近くから撮る場合と、遠くからズームを使って大きくして撮る場合で、
奥行きの方向の距離感がこんなに違うんですね。
今回は、文章の書き方ではなく、デジカメ写真の撮り方講座でしたが
千種先生が、プロジェクターと紙の資料で、
このようなズームを使った距離感の出し方や、
フラッシュのオンオフ方法、被写体以外に焦点を当ててからずらすぼかし方、
動くものをデジカメで撮る場合は少し先回りしてシャッターを押すことなど、
多彩で役に立つノウハウをいくつも教えていただけました。
また大島さんには、光の当て方で人の顔の深みや表情が全然違うこと、
撮る角度で被写体の雰囲気がガラッと変わることなど、
人物写真のプロのノウハウを直接教えていただきました。
はっきりいってこの授業、すごく役に立ちます。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
未来スクールはちおうじ第三回の巻
2010年09月12日
第三回「未来スクールはちおうじ」
学園都市センター12階セミナールーム
2010年8月14日
猛暑の中、「夏休みの自由研究を、大学の先生がお手伝い」という触れ込みで、
40組80名ほどの親子が集まりました。
午前と午後の2回に分かれ、
①「キッチンでできる化学実験」(薬科大 渡辺先生、成井先生)
②「まわしてみよう! ギリギリガリガリ」(拓殖大 渡辺先生)
③「しゃくとり虫型ミニロボットを作ろう!」(拓殖大 森先生)
④「透けて見える、小さな命。ミジンコの顕微鏡観察」(薬科大 高橋先生)
の4つが行われました。
①の「キッチン~」は、昔リトマス試験紙でやった酸性、
アルカリ性のチェックが、グレープジュースの色の変化でも、
できてしまうというもの。
(私たちのお腹の中の酸性度も、もしかしたら分かる?)
②の「ギリギリガリガリ」は、木をガリガリこする振動が伝わって、
木の先につけたプロペラを回す回転運動に変わるというもの。
③の「りゃくとり虫型ロボット」は、筋肉の働きをするバイオメタルを
取りつけて電気を流すと、くの字型の「ロボット」がたしかに歩きだしました。
④の「ミジンコ」は、顕微鏡でミジンコの心臓を見て、アルコールを入れる前後の
鼓動をカウント。酔っ払って拍数の増えたミジンコの様子を、
体を透かして確認する感じでした。
子どもたちは一様に「楽しかった」と言ってくれました。
親ごさんも楽しそうでした。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
テクニカル・カンファレンス第二回の巻
2010年09月09日
八王子未来学テクニカルカンファレンス第二回
八王子先端技術センター 開発・交流プラザ
高橋さん(拓殖大学副学長)、杉林さん(拓殖大学教授)、
前山さん(拓殖大学准教授)、香川さん(拓殖大学准教授)、
山口さん(明星大学教授)、
伊藤さん(東京高専准教授)、向川さん(東京高専技術職員)
2010年7月30日
今回のテクニカルカンファレンスには、企業も20社以上が参加していました。
拓殖大学の前山先生は、電波測定をテーマに発表されていました。
携帯電話の、ワンセグやオサイフケータイのような機能ごとの
電波測定法についてでした。電波無響室などの施設があるそうです。
同じく拓殖大の香川先生は、二足歩行ロボットの足についている複数の
「コントロール」について話されました。
産学連携の研究では、企業から持ち込まれるあいまいな質問にも答えつつ、
そのアイデアの試作品を作るようなこともされているそうです。
同じく拓殖大学の杉林先生は、新しいダイカスト金型について、
またスポット溶接についてお話されていました。
拓殖大学の産学連携研究センターはこちらのようです。
明星大学の山口先生は、昨年できた「連携研究センター」の
機能についての説明をされていました。
先生ご自身は、極低温測定、強誘電性、超伝導、熱伝導の研究をされているそうです。
東京高専の伊藤先生は
企業からの研究には段階があって、①依頼分析 ②技術相談 ③技術協力
④受託研究 ⑤共同研究 の順に進めばお互いに信頼を得られる。
いきなり共同研究をやるより、まずは、技術相談や依頼分析でお越しください、
と出席した企業の皆さんに話していました。
同じく高専の向川さんは、企業からの受託試験をして分析結果を出す際に、
ランニングコスト程度はもらうが、
基本的には非常に安くやっているので、気楽に持ち込んでほしい。
その結果を受けて、共同研究や受託研究に話を進められればいいのでは、
と話していました。
ちなみに東京高専の産業技術センターはこちらです。
この日は、ほとんど質問のなかった企業の皆さんも、
その後日をあらためて、先生にアクセスしていたようです。
うっかり質問はできませんよね。限界を見せることになるし、
やりたいネタもばれてしまう。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
八王子流地産地消
2010年08月30日
八王子流地産地消
桑の都・八王子復活 新品種桑「創輝」で街おこし
創価大学 押金名誉教授の55年にわたる桑の品種改良により
食用の新桑品種「創輝」が平成20年6月農水産省に品種登録された。
桑の研究に人生をかけられた開発者(押金名誉教授)の
精神(信念)を継承し、
長寿社会に健康面で貢献できる安全安心な商品を
創出することを使命に創輝株式会社が設立され、
八王子産学公連携事業(八王子市)・平成20年農商工等連携事業
(経済産業省・農水省主管)の認定を受け商品開発が始まった。
もともと桑はお茶とともに中国から薬として入って来た農産物であり、
お茶は日本人の食卓に合い、茶道文化としても浸透していった。
しかし、桑は漢方薬っぽく飲みにくいが、
栄養成分が豊富なため蚕の餌として活用された。
生糸産業の衰退により、豊富な栄養成分を活かす方法として、
桑の中にある成分(1-DNJ)が糖分の吸収を抑制し、
カルシウム、カリウム、鉄分、亜鉛などのミネラルが多く含まれ
食物繊維も多く効用が見込まれることから
食用としての開発研究が為されてきた。
「創輝」は通常の桑葉の三倍の大きさで,厚さもあり青々としており、
葉の成分を分析すると、養蚕用の品種に比べカルシウム1.2倍、
マグネシウム2.4倍を含んでいるとの事、
創価大学の久米川先生がこの葉をパウダーにする研究を
八王子産学公連携機構などの助けを得て
「創輝」の特性を活かした基礎研究を継続しています。
さらに、大学発ベンチャーの創輝㈱(本社八王子)は
大学や地元の契約農家などと協力し、創輝を大量栽培すると共に、
農地の拡大と育成方法の研究や量産化及び商品開発を進めています。
すでにお茶と飴は商品化されており道の駅八王子滝山店、
京王高尾山口駅売店他アンテナショップで販売されています。
パウダーを利用しての商品はいろいろ考えられるが、
作る物や作り方によりどの様な効用が見込まれるかを検討して頂きたく、
今日は東京家政学院大学の奈良先生と地域連携コーディネーターの山岡様に
岩重社長とお願いに訪問しました。
食物の効用については東京家政さんが第一人者と考えての訪問でした。
お二人とも興味を持ち聞いて頂き検討いただけるとのお話を頂く事が出来ました。
八王子の特産品を商業会の皆様と創出・販売することで、
食用による八王子「桑都」の復活と農家の活性化に貢献し、
商品が東京多摩地域や全国に広がることを期待しています。
首都大学東京の産学公交流会の巻
2010年08月29日
首都大学東京
南大沢キャンパス産学公交流会2010
2010年7月26日
南大沢の首都大学東京のキャンパスで、
産学公の交流会が開かれました。
研究室の成果を企業に積極的に訴えるとともに、
首都大学東京の南大沢キャンパスをみなさんに紹介する、
という趣旨だったようにも感じました。
その点、先日の電通大の「産学官連携DAY in 電通大」と少し印象が違いました。
いろいろな研究室を紹介する4つほどのコースが用意されていて、
参加者はそのどれかを選択、
私は流れによる振動で発電する装置や、マイクロ機械要素の研究を拝見し、
また、どのコースにも共通に組み込まれている牧野標本館を見学しました。
ここには「牧野富太郎博士が採集された植物標本を中心に、
藻類からコケ、シダ植物、裸子、被子植物にわたる標本が
約50万点所蔵」されているということです。
入ってみるとたしかに、実物の植物が入れられた「封筒」の「データベース」が、
巨大な棚群の倉庫に整然と保管されていました。
首都大学東京を特徴づける大きな資産のひとつだと思いました。
(今回、コーディネーター情報交換会でお会いした
首都大学東京の産学公連携コーディネータ・宗木さんからの
お誘いを受けて参加しました)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
ロボット講演の巻
2010年08月28日
創価女子短大・亀田さん(准教授)
NECで
2010年7月22日
「PaPeRoセミナー」が三田のNECビルで開かれ、
そこに創価女子短大の亀田さんや、
ジャイロウォークという会社の社長・石古さんが
ゲストでスピーチしていました。
亀田さんは、パペロの利用に興味を持った背景として、
岩手県川井村で行った「見守りシステム構築・運用経験」についての
紹介などを行っていました。
また、石古さんも、パペロというよりは、パペロに搭載したAR(拡張現実)
技術アプリの活用事例を紹介していました。
まだロボットそのものが見守りシステムやARの主役に
なるという段階ではありませんが、
NECがパペロなどのロボットに本腰を入れようとしている…
そんな気がしました。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
ボランティアセンター南大沢の「あいあいサー」の巻
2010年08月04日
八王子ボランティアセンター南大沢分室
大島さん(手前、八王子ボランティアセンター主査)
2010年6月26日
――八王子ボランティアセンターに「あいあいサー(あいあい祭ー)」というお祭りがあって
元横山町と、この南大沢の二つのボランティアセンターで行われているそうです。
主査の大島さんがいましたので、聞いてみましょう。
元横山町と南大沢では違いがあるんですか?
大島さん「元横山町ではあいあいサーは、5回、南大沢でも、今回で4回目です。
二つのあいあいサーにとくに違いはありません。地域分担をしています。
南大沢地域のボランティアさんを中心に企画・運営しています。
また、このような催しを通じて、ボランティアセンター南大沢分室の
認知度が高まれば、との期待もあります」
――そんな南大沢で行われるあいあいサーは、
様々な人が作ったお菓子や焼き鳥、竹トンボ、紙芝居、
室内では文章を音声にしたり点字にしたり、
また本そのものを作ったりするボランティアの皆さんの紹介や、
悩み相談の受付などが行われていました。
経済活動とはちょっと違う、気持ちの活動です」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
明星大学の連携研究センターの巻
2010年08月01日
明星大学 連携研究センター長室にて
右奥が、山口さん(明星大学教授 連携研究センター長)、
左奥から、大久保さん(未来学コーディネーター)、斎藤さん(未来学コーディネーター)
明星大学 連携研究センター
2010年6月17日
明星大学に連携研究センターができたという話を聞き、
どんなところか拝見しにやってきました。
■目的と特徴
――連携研究センターの目的は何ですか?
山口さん「大学と企業が共同研究したり、大学内の研究シーズを集めて、
それを地域の企業に使っていただいたりするための窓口です。
「研究協力」(学外との共同研究や受託研究)
「知的財産の提供」(特許などを積極的に外部で活用)
「研究設備の共同利用」(各種元素分析装置など最先端研究設備)
「その他の地域貢献」(専門教員の派遣など)
の四つが柱です」
■明星大学のセンターの特徴は何ですか?
山口さん「理工系だけでない「総合力」がウリです。
たとえば、「福祉機器開発」では、
人文学部の研究者が、障害者は何を求めているかを調査し、
理工学部の研究者が試作機器を開発するといった学部横断的な研究も進行中です。
その他に、電子顕微鏡もX線装置も複数種類あるように、
測定機器でいいものがあります」
――明星大学の中での位置づけはどうなっているのですか?
■経緯とこれから
山口さん「連携研究センターは、学内の共同利用実験装置を管理していた
物性研究センターと、
外部資金の受け入れ窓口だった事務組織が昨年、一緒になってできました。
連携研究センターは、学内外を結ぶ研究支援機関としての
位置づけを与えられたのです。
今年から科研費の申請の受け入れ業務もやることになりました。
また、外部からの共同研究や受託研究の窓口も行っていきますし、
企業交流イベントなどにも、積極的に参加していきます」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
南陽台地域福祉センターの巻
2010年07月25日
南陽台地域福祉センター
渡邉さん(理事長)
2010年6月17日
南陽台福祉センターの渡邉理事長をお尋ねしました。
「ロボット治験・社会福祉モニター」の試みについて伺うためです。
渡邉さんは、らいふねっとMOE理事長の菅原さんに紹介していただきました。
■介護保険の制度の使い勝手
――八王子の様々な施設でロボットの実験をする、ということは可能でしょうか。
渡邉さん「たとえば、車椅子に乗ったまま、
階段を上り下りできる「車椅子ロボット」があります。
バッテリーを積んでいて重いんですが、一段一段降りていく。
ただ、万一のときのために、うしろから支えます。
それは、うちも使いたいんです。
デイサービスは送迎があり、玄関などでの上り下りが大変だからです。
でも「壁」があります。レンタルで利用することができない、ということです。
介護保険では、利用者本人の申請でないと、レンタルできないのです。
そしてその装置は、その人のみに使えることになる。
となると、1台を複数の人に利用してもらう福祉施設では、難しい。
レンタルができないとなると購入しかありませんが、買えば1台百数十万円します。
高額である一方、車椅子ロボットは、
たとえばMOEと南陽台で1台あればいいくらいです。
この車椅子と同じことが、ロボットでも起こりかねない。
たとえば人が装着するタイプのロボットは、衰えた筋力をカバーするのが目的ですが、
それも利用者の申請で利用者だけが使うということになれば、
施設側では使いづらいでしょう。
ロボットなどの実証実験では、そういう点を考慮できるでしょうから、
複数の利用者で使えていいと思います。
要するに介護保険に問題があるんです。
このちぐはぐな制度を変えてほしいんですが、
それには政治の力が必要になってきます」
■超高齢化社会に備えて
「パぺロのようなロボットの実験なら、うちの施設でも可能です。
というのは、2015年~2020年の地域の福祉のあり方に、
私たちはとても興味があります。5年、10年後どうなっているか。
確実に超高齢者社会になるからです。
この南陽台は、高齢化率40.5%。
今は65歳以上の10%がなんらかの介護が必要なんですが、
9割のお年寄りは元気です。このあたりは、「ぴんぴんころり」が多い(笑)。
どうしてそうなっているのかを検証する必要がありますが、
見ていると、どうも、9割の人は、元気な時代に何かをやっているらしい。
それを楽しみとして続けている人が「ぴんぴんころり」。
フィンランドがそういう傾向が強い。
フィンランドでは、5、6件をまとめてグループとし、
それ全体を取りまとめて福祉が成っている。
ふつうの民間が、5、6件のネットワークを組んで、その中に、
アクティビティ(軽度の運動や遊び、趣味など、心身活性化のための手助け活動)や
癒し系のロボットが入る形のようです。
9月にフィンランドに、介護などの要員を派遣し、見学をしてきます。
理事会で承認されましたから
(南陽台地域福祉センターの理事会には8人の理事がいて、渡邉さんがその理事長)」
■ロボット治験 パペロ
「一人に1台使える装置というのではなく、共通で使えるものがやりやすい。
広く「治験」を利用するのは、必要でしょう。
南陽台は、40人の職員がいますし、パぺロなら、
広間に1台置いて使ってみるという使い方になります。
■盲導犬型ロボット
現在、この施設でサービスをしている範囲では、目の不自由な方はいません。
耳が先天的に不自由な方はいますが。
ただ、介護と医療の両方をやっていて、私たち介護事業者が
頼りにしている病院が近くにありますから、
そういった病院や盲学校がいいかもしれません。
<このブログは八王子未来学がおおくりしています>
八王子事典の巻 その5
2010年07月24日
八王子事典第一回編集専門委員会(東京高専)
奥の左から、望月さん(創価大准教授)、森さん(創価大教授)、
釜谷さん(工学院大准教授)、数馬さん(工学院大教授)、榎本さん(工学院大教授)、
岡戸さん(コンソーシアム)、設楽さん(コンソーシアム)、千種さん(工科大准教授)、
岩清水さん(東京高専、見えてないけど)、浅野さん(東京高専准教授)
2010年6月11日
「八王子事典(仮)」の第1回編集専門委員会が開かれました。
人気の学園都市センターは予約できず、場所は東京高専の多目的室です。
今回は第一回ということもあって、
まずは意見を出し合ってみる場でもあったかもしれません。
■査読
論文の世界には「査読」というものがあるそうです。
査読を受けたものが論文として認められる、みたいな。
「編集専門委員会に査読の機能を持たせましょう」
「査読は専門性が必要ですから、
ここに出席している先生だけでは、範囲の広い「八王子事典」は荷が重いのでは?」
「協力委員や、コンソーシアムを通じて八王子の23大学を紹介してもらい
役割分担をすればいいかも」
「査読して審査するところは、権威が必要でしょう」
■ユーザ
「まず小中学生(背伸びをした小学生と、中学生)がターゲット」
「とっかかりは、「歴史」と「風俗習慣(ファンキーモンキーベイビーズとか)」」
「若い人に使ってもらいましょう」
「中学生の夏休みの宿題で、たとえば産業→桑や絹織物、みたいに使えれば」
■コンテンツ
「先生の執筆とともに市民からの投稿を募集しましょう」
「教員が書くページ、訓練された人が書くページ、ブログ、の3つの分野があるかも」
「情報量が多いので、記事より写真がいいのでは?」
「写真を見せて、どこだかわかるか?というクイズもいい」
「八王子学でフォトコンテストをやりました。
テーマを与えて募集したところ、まだ数はそれほどではありませんが、
いい写真が集まりましたよ」
■協力委員は?
「八王子学会や八王子の桜を守る会といった市民の会に協力を
お願いするのはどうでしょう」
■当面の項目選び
「A先生、千人同心やその周辺+スポーツ、
B先生、生物中心、動植物、
C先生、日本史20項目、
D先生、産業の一部なら。
E先生、校内から先生を紹介、
F先生、ま、こんな感じで、とりあえず項目案を出してみましょう」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
電通大の産学連携の巻
2010年07月23日
「産学官連携DAY in 電通大」
電気通信大学
2010年6月2日
調布にある電通大で、「産学官連携DAY in 電通大」という
産学連携イベントがありました。
企業から研究テーマが持ち込まれるのを待つだけでなく
積極的に研究室を公開していくためのイベントだということです。
上の写真は、学生のアイデアを紹介する発表会で、
大勢の企業関係者が押しかけている、といった感じでした
(個人的には、甲羅の上に植物を配置して、水を自動でさして育てる
カメロボット<植物と動物の中間を狙ったとか>が、
面白いと思いました。他にもキーが4つしかない日本語入力装置や
非難の言葉がどんな痛みを引き起こすかを感じるシステム、
などなどいろいろな提案が出ていました。
いい審査結果が出て研究費が出るといいですね)。
とても盛り上がっていましたし、高専などと比べて、
その規模の大きさと層の厚さに、当然なんでしょうが、驚きました。
ここに誘ってくださったのは、
先日のコーディネーター情報交換会に出席し、
「電通大の得意分野はITです。ITの連携はどうぞ電通大へ」とおっしゃっていた
電通大産学官連携センター特任教授・河野さんです。
産学連携を模索していらっしゃる皆さん、
電通大の今回、6回目というこのイベントに
一度行かれるといいと思いました。
京都や南大阪に行かなくても、面白いものは意外と地元にありそうな。。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
コーディネータ情報交換会の巻
2010年07月01日
八王子先端技術センター開発・交流プラザ会議室
八王子市産業振興部・大西主幹、八王子市産業政策課・柏田主査、
八王子市産業政策課・奈良主任、
JST産学連携展開部・田中主査、都産技研・瀧山産学公連携コーディネーター、
中小企業振興公社多摩支社・和田統括コーディネーター、
八王子先端技術センター・川崎相談員、同・沖川相談員、
TAMA協会・竹内事務局次長、TAMA協会・小林マネージャー、
サイバーシルクロード・土方サブリーダー、(同・高橋事務局次長)、
首都大学東京産学公連携センター・宗木コーディネーター
TAMA-TLO・松永事業部長、農工大TLO・大平アドバイザー、
電通大産学官連携センター・河野特任教授、
TAMA-TLO・武田コーディネーター、大学コンソーシアム・竹中主任、
八王子未来学コーディネーター・大久保、斎藤、出口
2010年5月20日
平成12年度の企業支援総合コーディネート事業は、八王子市が
「地域企業のためのワンストップ相談所」を目指しているプロジェクトのようです。
よろず相談所ですね。南大阪地域コンソーシアムと違うのは、
大学が中心にあるわけではない、ということだと思います。
(大学関係では、首都大学東京、電通大、農工大、そして高専が参加していますが)
まず、文科省のJST産学連携展開部の田中さんから、
22年度の補助金の数々が説明されました。
それを皮切りに、様々な意見交換がされましたが、
白熱したのは、産業と大学、つまり産学コーディネートのやり方と、
そのコーディネーターがこの場で何を話し合うべきか、ということでした。
・先端の技術から、派生していろいろな技術が生まれるので、先端技術を話してもらう。
・いや、10年後の先端の手前の1~3年の技術が、企業には必要なのだ。
・(専門を深く掘り下げる)I字型もいいが、それだけではだめで、
(幅を持った)V字型の知識が必要だ。
・大学の先生は、先端の深さをさらに掘ったところをやる。
だから、1~3年先を見ている企業とは、もともと合わない。
・先端よりむしろ、少し古いくらいの技術の方が、企業に受け入れられる。
・コーディネーターの出身母体が、何が得意なのかを言うべき。そうすれば、
この案件は、得意なあのコーディネーターの投げてみよう、と考えることができる。
今回、電通大が、ITが得意だと言ってくれたのはとてもいい。
・いや、得意分野ではない、切り捨てられる他の分野にも光るものがたくさんある。
だから得意分野を言うのが必ずしもいいわけではない。
・コーディネーターが、信頼されて、やっと企業に本音を言ってもらえる
(企業はニーズを含めた本音を言わない)。
この場では、公にはできないことでも、コーディネーター間の
情報を持ち寄って、相談するのがいい。
知識と知識の交換ならまだいいですが、そこに秘密情報も絡んでくると、
なかなか難しいですね。
たとえば結婚情報も、自分についての教えたい情報と、
教えたくない情報があり、お互いのそれを全部知っている仲人がいたら、それは神様でしょう。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
Posted by コーディネーターズ at
23:18
│Comments(0)
八王子事典の巻 その4
2010年06月30日

工学院大学 新宿キャンパス
数馬さん(工学院大学教授)
2010年5月24日
―八王子事典にどんなことを希望されますか?
数馬さん「一般の市民の方の記事も、重要な点を含む場合がありますから、
事典にアップしていったらいいと思います。
でも、専門家による記事と、自由に書ける記事を分けた方がいい。
また、たとえば同じ千人同心についての専門家による記事でも、
A先生が書いた記事と、B先生が書いた記事の見解が異なる場合があります。
そこを、たとえば専門委員会が「専門委員会の見解」として、
「AさんとBさんの記事は、この部分が異なるが、
どちらも歴史には矛盾しない」といった
文章を載せるといったことも考えるべきかもしれません。
レアなケースも考えておくべきでしょう。
また、論文を論文としてチェックするシステムもあった方がいいと思います」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
ボランティア活動
2010年06月28日
杏林大学保健学部西村先生、
山野美容芸術短期大学美容芸術学科鎌田先生、武藤先生で
八王子市老人クラブ連合会(八老連)に
ボランティアの実施のお願いでお邪魔しました。
大学では今地域への貢献と学生さんの教育に力を入れており、
今回の訪問と成りました。
八老連は支部数19支部、単会クラブ数210クラブ、
会員数14,500名と大変多くの会員数を持つ組織で
総務部、広報部、研修部、健康増進部、生きがい部、女性部が在り
多彩な行事の催しと社会への奉仕活動を行なっております。
今日は橋本晴重郎会長、稲川芳江副会長に面談戴き、
西村先生から「アロマ」を使用したお香や石鹸作りの提案、
鎌田、武藤両先生からハンドマッサージの提案をして頂きました。
橋本会長、稲川副会長も大変積極的な方で会員のために
成ることはどんどん取り入れをしていきたいとのこと、
まずは単会のどこかで取り入れをし、そこから広げていくようにして行きたいとの事、
難しいのは継続をして行けるか、また費用をどうしたら良いか等の問題もあるが、
一つの成功が他に拡がって行きそれぞれのクラブで催され、
引きこもりの人たちが参加するように成って頂ければ、
クラブの課題も一つ減ることに成るのでは無いでしょうか。
Posted by コーディネーターズ at
15:25
│Comments(0)
八王子の公園その7
2010年06月18日
八王子の公園その7

5月10日拓殖大学八王子キャンパス
シビックデザイン研究室内にて中間発表会が、
八王子セミナーハウスから池田課長、熊木課長、酢屋推進役、
公園指定管理者日産マルベリーパークから管理責任者鈴木さん、
八王子未来学から大久保、斎藤コーディネーターをオブザーバーに開催されました。
4月17日に柚木めぐみ野緑地の現地視察を行った学生さん11名から
其々の思いを込めた発表が行われました。
①間伐材活用によるトレイルランコース・・マラソンや登山ブームに乗って
②森の中のサイクリングコース・・エコな、自転車の楽しさを多くの人に
③木々のチャレンジ・・自然を残し、ツリーハウスやハンモックで癒し
④音の力に注目した里山ブランディング・・鳥や虫の自然の音、
ハウスでの演奏会の音、ビアガーデンで地域交流
⑤サバイバルゲーム・・森の野戦、セミナー未開発広場の利用
⑥自然を活かした緑地の観光スポット化・・スピリチュアルスポット滝から
手打ちそば体験
⑦めぐみのホタル・・ホタルや緑地の生態系保護から環境教育
⑧癒しを求めた八王子セミナーハウス・・近隣とのふれあい、大人、子供、
森のお絵かきコース
⑨環境教育を体験する遊び場・・遊んで学べるフィールドアスレチック
⑩古くて新しい妊婦生活(世代を超えて愛されるセミナーハウス)・・妊婦の
交流と健康の促進
⑪トイカメラ貸し出しによる自然体験・・流行のトイカメラで自然体験研修
と11通りの提案がなされた。
担当の永見先生はデザインの扱う領域は、従来は「モノ」が中心でしたが
現在は「モノ」を使う「シーン」の提案から「サービス」まで領域が広がっており、
3年生の前期授業デザインシステム演習1の課題として
八王子セミナーハウスと隣地の柚木めぐみ野緑地の利用計画をテーマに設定し、
これまで学んできたプロダクトデザインや環境デザインの視点を応用展開すること、
具体的な場所での一連のデザインワークを体験することを狙いとした為との事です。
他の大学でも同様な研究をしていられるようでしたら、
学生の交流も兼ねて連携して一緒に学べると良いのですが、声を掛けてください。
5月10日拓殖大学八王子キャンパス
シビックデザイン研究室内にて中間発表会が、
八王子セミナーハウスから池田課長、熊木課長、酢屋推進役、
公園指定管理者日産マルベリーパークから管理責任者鈴木さん、
八王子未来学から大久保、斎藤コーディネーターをオブザーバーに開催されました。
4月17日に柚木めぐみ野緑地の現地視察を行った学生さん11名から
其々の思いを込めた発表が行われました。
①間伐材活用によるトレイルランコース・・マラソンや登山ブームに乗って
②森の中のサイクリングコース・・エコな、自転車の楽しさを多くの人に
③木々のチャレンジ・・自然を残し、ツリーハウスやハンモックで癒し
④音の力に注目した里山ブランディング・・鳥や虫の自然の音、
ハウスでの演奏会の音、ビアガーデンで地域交流
⑤サバイバルゲーム・・森の野戦、セミナー未開発広場の利用
⑥自然を活かした緑地の観光スポット化・・スピリチュアルスポット滝から
手打ちそば体験
⑦めぐみのホタル・・ホタルや緑地の生態系保護から環境教育
⑧癒しを求めた八王子セミナーハウス・・近隣とのふれあい、大人、子供、
森のお絵かきコース
⑨環境教育を体験する遊び場・・遊んで学べるフィールドアスレチック
⑩古くて新しい妊婦生活(世代を超えて愛されるセミナーハウス)・・妊婦の
交流と健康の促進
⑪トイカメラ貸し出しによる自然体験・・流行のトイカメラで自然体験研修
と11通りの提案がなされた。
担当の永見先生はデザインの扱う領域は、従来は「モノ」が中心でしたが
現在は「モノ」を使う「シーン」の提案から「サービス」まで領域が広がっており、
3年生の前期授業デザインシステム演習1の課題として
八王子セミナーハウスと隣地の柚木めぐみ野緑地の利用計画をテーマに設定し、
これまで学んできたプロダクトデザインや環境デザインの視点を応用展開すること、
具体的な場所での一連のデザインワークを体験することを狙いとした為との事です。
他の大学でも同様な研究をしていられるようでしたら、
学生の交流も兼ねて連携して一緒に学べると良いのですが、声を掛けてください。
Posted by コーディネーターズ at
13:41
│Comments(0)
八王子事典の巻 その3 城山中学校編
2010年06月12日

八王子市立城山中学校
鈴木さん(城山中学校校長)
2010年5月19日
―八王子事典をネット上に作るにあたって、大学や高専の研究室を
中学生に取材していただけないでしょうか。
とくに今回は東京高専なんですが、
ロボット大会に出場したロボットや、校庭を歩きまわっているヤギなど、
中学生が興味を持ちそうな研究がたくさんあります―
鈴木先生「大学や高専の研究室を中学生が取材するというのは、
基本的に面白いと思います。
うちの中学校でも、生徒の職場体験というのがあって、
中学生3年生が、取材を含めた体験をしています。
ただ、中学生に、研究室を取材する力量があるかどうか、不安です」
―その点では、「取材の講義」をしてくださる先生方がいます。
中学生に記事の書き方や写真の撮り方などを教えてくれるはずです―
鈴木先生「取材の講義も取材も夏休み中がいいですね」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
南大阪地域大学コンソーシアムの巻
2010年06月03日

多摩永山情報教育センター
第2回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナー第3分科会 「大学連携」
2010年3月15日・16日
―3月の半ばの二日間、永山の研修センターで
八王子未来学ニューFD/SDセミナーが開かれました。
泊りがけで、いろいろな分科会に分かれて討議が行われましたが、
その中の南大阪コンソーシアムのコーディネーター難波さん(写真)の講演から、
南大阪地域大学コンソーシアムがうまくいっている理由について、
まとめさせていただきました。
難波さんは、有限会社ダブル・ワークスの代表取締役で、
南大阪地域大学コンソーシアム統括コーディネーターです。
2001年に大学や学会を知的にサポートする
大学発ベンチャー・ダブルワークスを設立され、
今では大学と地域をつなぐコーディネーターの役割が中心になっているそうです―
■1■うまくいっている理由
●理由1 事務局運営を企業に委託
この会社は、大学や学会のサポートすることを目的に設立されたベンチャーです。
当時は、全国初の女子大発ベンチャーとして注目されました。
ふつう、大学コンソーシアムは大学の事務局が運営しますが、
南大阪では、大学関連の「企業」に事務局運営を委託しています。
このような事例は他にはあまりありません。
この企業が、様々な事業運営の中心的役割を果たしており、
委員会の運営、事業実践のほか、産官学地域連携で重要なコーディネータの役割や、
国や自治体の補助金や公募事業に対して申請書類を作成したり、
事務処理を行っています。
事務局には、委託企業のほかに専任職員がおり、
大学と連携しながら一体となった運営を行っています。
企業が行うことで、特定の大学に与することなく、
こういった仕事に長期にわたって継続的に責任を持ち続けられる利点があります。
(学生は数年経てばいなくなるし、大学や市の職員は自分の仕事に追われています)
●理由2 窓口の1本化
この地域の大学に対する依頼の受付として、窓口を
大学コンソーシアムで一本化しています。
言い方を変えれば地域の「ヨロズ相談所」です。
●理由3 研究者データベースあり
地域の大学の研究者データベースがあり、大学の先生の名前と
研究内容が検索できます。
これは、小さな大学でも地域貢献に参加できる可能性を広げるということを意味します。
小さくても大学の外との窓口ができ、産学官地域連携の
促進につながる、ということです。
ただ、知の連携のテーマは難しいですよ。
●理由4 学生主体で使い勝手よく
南大阪のコンソーシアムは、学生が主体です。
学生がチームの大切さを学びながら、企業と真剣勝負する場でもあります。
それは、企業からの依頼の案件で、そのおカネを学生に支払っているからです。
企業も、おカネを出している以上、100点でないとOKを出しませんから、
学生も真剣になります。
取組みによって支払われる金額は変わりますが、例えば、
ブレーンストーミングなどへの参加は2時間で5千円です。
成果は卒論に使ってもいいという方針も奏功しています。
そういった真剣さが、学生国際ショートムービー映画祭商談会オークションで、
企業が学生を落札する、という結果にも結びついています
このようにすべての事業を学生中心に行っていて、結果的にですが、
「人づくり」にもなっていました。大学からの期待が大きい部分です。
こういった育て方が、うちのコンソーシアムと組む事業を
増やしているという側面もあります。
●理由5 受託収入を高確率で獲得
収入の内訳は、(自治体、経産省や文科省などからの)受託収入が9割です。
残りの10%は、各事業会社負担、コンソーシアムの事業収入、
会員収入、となっています。
背景には、現在までのところ自治体や国などの事業を高確率で受託できている、
という事情があります。
でも、事務局運営をどう充実させ、安定した運営費をどうねん出するかは、
大きな課題です。
―また「うまくいっている理由」以外にも、
難波さんはいくつもの重要なことをおっしゃっていましたが、
その中から、「コンソーシアムの副産物」や「連携を円滑に進める方法」
「大学連携とコンソーシアムの違い」などについても、
箇条書になりますが、お伝えします―
■2■効果と副産物
●知的資源の共有
ひとつのプロジェクトに各大学の学生を集めることで、知的資源を共有できる。
●窓口一本化の効果
小さな文系大学の先生にも、コンソーシアムを通じて研究費を渡せる。
●異文化交流
学生同士の交流促進で相互に刺激あうことができる。
●授業への効果
コンソーシアムで育んだ知的資源(各種講座、効果測定、ユニークな
人材育成プログラム等)を大学の科目に還元することでができる。
■3■温度差のある大学同士を連携させて円滑に進める方法
以下のように、大学連携が大学にもたらすものを明確にして説得する
●デメリット
・競争相手とやらなくても、一人でやる方が簡単。
・他の大学とは文化が違う。
・他の大学(の先生や事務は)何を考えているか分からない
・連絡が大変。
●メリット
・10大学でやれば1/10のコストで済むので効率的。
・一人でやるより大勢でやった方が、スケールメリットがある。
・異文化交流あり。
・全体であたることが必要な共通の課題と、
各人があたれば済む固有の課題を区別することができる。
・社会的信用が増す。
■4■大学連携とコンソーシアムの違い
―現在、八王子が目指している連携には、学学連携や産学(官)連携があって、
大学のシーズと地元のニーズを結びつける、という産学連携も
八王子未来学に課されていましたが、
八王子未来学や大学コンソーシアム八王子が目指している
連携のメインは、学学連携です。
しかしその学学連携の中での「大学連携」と「大学コンソーシアム」を、
明確に区別したことはなかったように思います。その点について、
難波さんは整理してくださっています―
●大学連携
・大学に内在している。
・分担したり、合理化することで「引き算、掛け算」の発想になる。
・地域の知の拠点の確立を目指す。
・経営の効率化の実現を目指す。
●大学コンソーシアム
・大学に外在している。
・大学の人材や研究をつなぎ合わせる「足し算」の発想。
・地域の学術機能の向上。
・産学官、地域の連携推進を目指す。
●大学とコンソーシアム事業のそれぞれの特色
・アカデミックな大学⇔社会との接点を演出するコンソーシアム
■5■なぜ大学コンソーシアムが必要か(結果としてということでもある)
―そのうえで、なぜ、大学コンソーシアムが必要なのか、を難波さんは問うています―
・大学に対する社会の期待が大きくなった。
・社会が多様化。複雑化する中、ひとつの大学でできることが限られてきた。
・大学単体での体力が相対的に弱体化。→経営効率化SD
―いかがでしょう、難波さんの6倍速の講義についていくのは大変で、
とても内容の濃い講演だったのですが、今回はその一部を紹介させていただきました。
整理してみて、その重要性に気付いた次第です―
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
家政学院大学の食材の研究の巻
2010年06月02日
東京家政学院大学
(向かって右から)小口さん(家政学院大学准教授)、山﨑さん(家政学院大学講師)、
Aさん(某製薬会社)
2010年5月11日
ある製薬会社のAさんが、食材開発について
どんなことを行っていらっしゃるかを尋ねに
東京家政学院大学にやってきたところをご一緒させていただきました。
両先生を紹介してくださったのは、いつものように白井先生でした。
■小口先生
「現在は各地域の新しい食材を使って、新食感などを研究していいます。
おもに、利用しにくいものをどう再利用し、
新しい食材として使うか、といったことです。
米など、いろいろな素材を活用しようとしています。
企業との共同の研究もしておりますが、
研究の結果、家庭で作る食事としてはいいものができても、
大量生産、大量輸送の必要な企業から見る評価は異なる、ということがありました。
でも企業の評価に、大学としてはふりまわされてもいけないでしょう。
また別の成果として、学生の発想にはすばらしいものがあると思いました」
■山﨑先生
「現在の私が行っている研究の中心は、「食用花」から抽出した成分による
新機能性の探索や自然界からの有用微生物の分離・活用です。
また企業との連携では、コンセプトをお聞きし、
その内容を学生自身が消化して、進めています。
その中で、新商品のコンセプトも学生が設定し、新しい物が出来上がりました。
こちらでもやはり、学生の発想の豊かさには驚かされています」
■Aさん
「いろいろな健康食品を開発してきた人が関連会社にいます。
本日、教えて頂いたことを伝えたいと思います」
■小口先生と山﨑先生
「授業展開では現在、2つの企業に絞って行っています。
授業とは別に、各教員、数社と共同研究を進めていますが、
あくまでも教育を軸として、企業の方々の請負ではなく、
学生さんに学びの場となるかを根底に連携は進めていますので、
お話をいただいても、恐縮ですが、必ず連携できるというわけではありません」
<このブログは八王子未来がコーディネーターがおおくりしています>
Posted by コーディネーターズ at
18:03
│Comments(0)
パペロの会話システムの巻
2010年05月12日

NECビル(田町)
大中さん(NECプラットフォームマーケティング戦略本部 理学博士)
2010年4月28日
――パぺロの会話システムをプログラムするのは、難しいんですか?
大中さん「パペロ専用のプログラミング言語を使って
会話を組み立てるやり方もありますが、
ブロックを組み立てるように、会話を作っていくこともできます。
しかし現状では、「今日は天気がいいね」という文章を、
ひとつの単語のように認識するやり方ですから、
ユーザーのクセが「今日はお天気がいいよね~?」という言い方だと
そのように登録して、似たパターンの中から、ユーザーが何を言ったか
検索することになります。
事前に登録しておくそのパターンがあまり多いと、
検索に時間がかかることになり、応答が遅くなったりします。
そのパターン書き込みのプログラムを、
いろいろな学生さんや中高生にトライしてもらうのは、いいことだと思います」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>