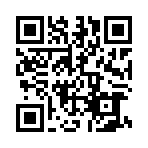東京家政学院大学でのロボット治験の巻
2011年01月29日
■1■ロボット治験・パペロのお願い(東京家政学院大学)

東京家政学院大学
前列左から中村さん(東京家政学院大学・非常勤講師)、吉川さん(同教授)、
小野さん(同教授)、市原さん(同教授)
後列左から飯谷さん(東京家政学院総務課課長)、大中さん(NEC)
2010年11月24日
今日は、パペロのロボット治験のプレゼンです。
「ロボットを使う幼児教育」の可能性に、総務課の飯谷さんが、すぐに紹介くださり、
飯谷さんが集めてくださった先生方も、ロボットが役に立つかどうか分からない状態で
興味を持っていただき、この後の、1カ月もしない期間の授業で
二度も「実験」を行なっていただけることになりました。
先生方の瞬発力に、少し驚きました。
■2■ロボット治験・パペロのプログラミング実習(東京家政学院大学)

東京家政学院大学
左から大中さん(NEC)、小暮さん(同)、田尻さん(東京家政学院大学助手)、
市原さん(同教授)、中村さん(同)、吉川さん(同教授)ら
2010年12月1日
NECから、プログラミングのコーチの小暮さんが来て、
みんなの前で、パペロの言動のコーチ&プログラミングをしてくれました。
先生たちから、「もう少しそこのイントネーションはこうならない?」
などといった要望がたくさんあり、小暮さんも汗をかいていました。
でもそのおかげで、ほぼ完成に近いプログラムが、この日にできてしましました。
クリスマスバージョン授業のプログラムもあり、
最終的には、小暮さんと田尻さんの間で、何回もやり取りを行い、
小暮さんは、もう一度プログラミングをしに来てくださったそうです。
■3■ロボット治験・パペロの実施1(東京家政学院大学)

東京家政学院大学プレイルーム
幼児グループの実習
2010年12月8日
今日は、東京家政学院大学で、幼児十数人と親、学生、教員によって
行われている幼児グループ実習で、
ロボットのパペロが子どもたちに、どう受け入れられるか、
パペロが「お片付けをしましょう」などと言った場合、
子どもたちは、保育者がピアノを弾いて伝える場合とどう違うのか、
などの観点から、「ロボット治験」が行われました。
一言で「行われました」と言っても、
ロボットを使うことをお母さんたちに説明し、理解を求め、
場面場面のプログラミングを行ない、
使う音楽についてはパペロに録音しと、とても大変です。
■4■ロボット治験・パペロの実施2(東京家政学院大学)

東京家政学院大学プレイルーム
幼児グループの実習
2010年12月15日
今日は、クリスマスにちなんだ実習で、
サンタクロースのお爺さんが登場し、
子どもたちがみんなプレゼントを受け取っていました。
パペロの存在に1回目より親しみを感じ、
「片付けられるか見ているよ」というパペロの声に、
片付けを見守ったり、励まされたりする子どももいたようです。
■5■ロボット治験・パペロの新年のロボット研究会(東京家政学院大学)

東京家政学院大学
左から、小野さん、大中さん(NEC)、吉川さん、田尻さん
2011年1月19日
今回は、12/8と12/15に行われた幼児グループの実習を受けて、
幼児教育におけるロボットの効果などが話し合われました。
・ロボットが集団の中の人間同士をつないだり、
三者関係を作るのに役立つ可能性がある。
(ロボットに「もっと早く起きなさい」と言わせれば、
お母さんが口やかましく言う必要もないし)
・2、3歳の子どもは、(外界に対し)アクションを起こし、その応答を見て、
またアクションを起こす、というサイクルで興味を覚え成長するので、
ロボットの応答が大切。
・ミラーニューロンで、他人に同調する機能はどう影響を受けるか。
・予想外にふるまうロボットを見て、「すべて自分が悪く、自分の責任」と
落ち込む人の思考パターンを変えていくことに、好影響?
・子どもを見守る存在としての機能が面白い。
などなど、こんなことに役立ってくれればという事柄が、並びました。
一方、子どもが相手なので、
・ロボットの隙間に手をつっこんだり、投げ飛ばす恐れがあるので、
人間が誰かついていなくては。
・触るとロボットが反応するエリアがよく分からない。
結論的には、もっと使ってみたいのだけど、
本格的に使うとなると、おカネもかかるし、なにがしかの助成金が出れば、
ということだったと思います。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
東京家政学院大学
前列左から中村さん(東京家政学院大学・非常勤講師)、吉川さん(同教授)、
小野さん(同教授)、市原さん(同教授)
後列左から飯谷さん(東京家政学院総務課課長)、大中さん(NEC)
2010年11月24日
今日は、パペロのロボット治験のプレゼンです。
「ロボットを使う幼児教育」の可能性に、総務課の飯谷さんが、すぐに紹介くださり、
飯谷さんが集めてくださった先生方も、ロボットが役に立つかどうか分からない状態で
興味を持っていただき、この後の、1カ月もしない期間の授業で
二度も「実験」を行なっていただけることになりました。
先生方の瞬発力に、少し驚きました。
■2■ロボット治験・パペロのプログラミング実習(東京家政学院大学)
東京家政学院大学
左から大中さん(NEC)、小暮さん(同)、田尻さん(東京家政学院大学助手)、
市原さん(同教授)、中村さん(同)、吉川さん(同教授)ら
2010年12月1日
NECから、プログラミングのコーチの小暮さんが来て、
みんなの前で、パペロの言動のコーチ&プログラミングをしてくれました。
先生たちから、「もう少しそこのイントネーションはこうならない?」
などといった要望がたくさんあり、小暮さんも汗をかいていました。
でもそのおかげで、ほぼ完成に近いプログラムが、この日にできてしましました。
クリスマスバージョン授業のプログラムもあり、
最終的には、小暮さんと田尻さんの間で、何回もやり取りを行い、
小暮さんは、もう一度プログラミングをしに来てくださったそうです。
■3■ロボット治験・パペロの実施1(東京家政学院大学)
東京家政学院大学プレイルーム
幼児グループの実習
2010年12月8日
今日は、東京家政学院大学で、幼児十数人と親、学生、教員によって
行われている幼児グループ実習で、
ロボットのパペロが子どもたちに、どう受け入れられるか、
パペロが「お片付けをしましょう」などと言った場合、
子どもたちは、保育者がピアノを弾いて伝える場合とどう違うのか、
などの観点から、「ロボット治験」が行われました。
一言で「行われました」と言っても、
ロボットを使うことをお母さんたちに説明し、理解を求め、
場面場面のプログラミングを行ない、
使う音楽についてはパペロに録音しと、とても大変です。
■4■ロボット治験・パペロの実施2(東京家政学院大学)
東京家政学院大学プレイルーム
幼児グループの実習
2010年12月15日
今日は、クリスマスにちなんだ実習で、
サンタクロースのお爺さんが登場し、
子どもたちがみんなプレゼントを受け取っていました。
パペロの存在に1回目より親しみを感じ、
「片付けられるか見ているよ」というパペロの声に、
片付けを見守ったり、励まされたりする子どももいたようです。
■5■ロボット治験・パペロの新年のロボット研究会(東京家政学院大学)
東京家政学院大学
左から、小野さん、大中さん(NEC)、吉川さん、田尻さん
2011年1月19日
今回は、12/8と12/15に行われた幼児グループの実習を受けて、
幼児教育におけるロボットの効果などが話し合われました。
・ロボットが集団の中の人間同士をつないだり、
三者関係を作るのに役立つ可能性がある。
(ロボットに「もっと早く起きなさい」と言わせれば、
お母さんが口やかましく言う必要もないし)
・2、3歳の子どもは、(外界に対し)アクションを起こし、その応答を見て、
またアクションを起こす、というサイクルで興味を覚え成長するので、
ロボットの応答が大切。
・ミラーニューロンで、他人に同調する機能はどう影響を受けるか。
・予想外にふるまうロボットを見て、「すべて自分が悪く、自分の責任」と
落ち込む人の思考パターンを変えていくことに、好影響?
・子どもを見守る存在としての機能が面白い。
などなど、こんなことに役立ってくれればという事柄が、並びました。
一方、子どもが相手なので、
・ロボットの隙間に手をつっこんだり、投げ飛ばす恐れがあるので、
人間が誰かついていなくては。
・触るとロボットが反応するエリアがよく分からない。
結論的には、もっと使ってみたいのだけど、
本格的に使うとなると、おカネもかかるし、なにがしかの助成金が出れば、
ということだったと思います。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
東京高専・加藤研の研究の巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
城山中学の中学生が東京高専の研究室を取材するの巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
城山中学の中学生が東京高専の研究室を取材するの巻
Posted by コーディネーターズ at 23:05│Comments(0)
│学校・学生・就職活動
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。