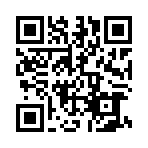八王子事典の巻 その4
2010年06月30日

工学院大学 新宿キャンパス
数馬さん(工学院大学教授)
2010年5月24日
―八王子事典にどんなことを希望されますか?
数馬さん「一般の市民の方の記事も、重要な点を含む場合がありますから、
事典にアップしていったらいいと思います。
でも、専門家による記事と、自由に書ける記事を分けた方がいい。
また、たとえば同じ千人同心についての専門家による記事でも、
A先生が書いた記事と、B先生が書いた記事の見解が異なる場合があります。
そこを、たとえば専門委員会が「専門委員会の見解」として、
「AさんとBさんの記事は、この部分が異なるが、
どちらも歴史には矛盾しない」といった
文章を載せるといったことも考えるべきかもしれません。
レアなケースも考えておくべきでしょう。
また、論文を論文としてチェックするシステムもあった方がいいと思います」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
ボランティア活動
2010年06月28日
杏林大学保健学部西村先生、
山野美容芸術短期大学美容芸術学科鎌田先生、武藤先生で
八王子市老人クラブ連合会(八老連)に
ボランティアの実施のお願いでお邪魔しました。
大学では今地域への貢献と学生さんの教育に力を入れており、
今回の訪問と成りました。
八老連は支部数19支部、単会クラブ数210クラブ、
会員数14,500名と大変多くの会員数を持つ組織で
総務部、広報部、研修部、健康増進部、生きがい部、女性部が在り
多彩な行事の催しと社会への奉仕活動を行なっております。
今日は橋本晴重郎会長、稲川芳江副会長に面談戴き、
西村先生から「アロマ」を使用したお香や石鹸作りの提案、
鎌田、武藤両先生からハンドマッサージの提案をして頂きました。
橋本会長、稲川副会長も大変積極的な方で会員のために
成ることはどんどん取り入れをしていきたいとのこと、
まずは単会のどこかで取り入れをし、そこから広げていくようにして行きたいとの事、
難しいのは継続をして行けるか、また費用をどうしたら良いか等の問題もあるが、
一つの成功が他に拡がって行きそれぞれのクラブで催され、
引きこもりの人たちが参加するように成って頂ければ、
クラブの課題も一つ減ることに成るのでは無いでしょうか。
Posted by コーディネーターズ at
15:25
│Comments(0)
八王子の公園その7
2010年06月18日
八王子の公園その7

5月10日拓殖大学八王子キャンパス
シビックデザイン研究室内にて中間発表会が、
八王子セミナーハウスから池田課長、熊木課長、酢屋推進役、
公園指定管理者日産マルベリーパークから管理責任者鈴木さん、
八王子未来学から大久保、斎藤コーディネーターをオブザーバーに開催されました。
4月17日に柚木めぐみ野緑地の現地視察を行った学生さん11名から
其々の思いを込めた発表が行われました。
①間伐材活用によるトレイルランコース・・マラソンや登山ブームに乗って
②森の中のサイクリングコース・・エコな、自転車の楽しさを多くの人に
③木々のチャレンジ・・自然を残し、ツリーハウスやハンモックで癒し
④音の力に注目した里山ブランディング・・鳥や虫の自然の音、
ハウスでの演奏会の音、ビアガーデンで地域交流
⑤サバイバルゲーム・・森の野戦、セミナー未開発広場の利用
⑥自然を活かした緑地の観光スポット化・・スピリチュアルスポット滝から
手打ちそば体験
⑦めぐみのホタル・・ホタルや緑地の生態系保護から環境教育
⑧癒しを求めた八王子セミナーハウス・・近隣とのふれあい、大人、子供、
森のお絵かきコース
⑨環境教育を体験する遊び場・・遊んで学べるフィールドアスレチック
⑩古くて新しい妊婦生活(世代を超えて愛されるセミナーハウス)・・妊婦の
交流と健康の促進
⑪トイカメラ貸し出しによる自然体験・・流行のトイカメラで自然体験研修
と11通りの提案がなされた。
担当の永見先生はデザインの扱う領域は、従来は「モノ」が中心でしたが
現在は「モノ」を使う「シーン」の提案から「サービス」まで領域が広がっており、
3年生の前期授業デザインシステム演習1の課題として
八王子セミナーハウスと隣地の柚木めぐみ野緑地の利用計画をテーマに設定し、
これまで学んできたプロダクトデザインや環境デザインの視点を応用展開すること、
具体的な場所での一連のデザインワークを体験することを狙いとした為との事です。
他の大学でも同様な研究をしていられるようでしたら、
学生の交流も兼ねて連携して一緒に学べると良いのですが、声を掛けてください。
5月10日拓殖大学八王子キャンパス
シビックデザイン研究室内にて中間発表会が、
八王子セミナーハウスから池田課長、熊木課長、酢屋推進役、
公園指定管理者日産マルベリーパークから管理責任者鈴木さん、
八王子未来学から大久保、斎藤コーディネーターをオブザーバーに開催されました。
4月17日に柚木めぐみ野緑地の現地視察を行った学生さん11名から
其々の思いを込めた発表が行われました。
①間伐材活用によるトレイルランコース・・マラソンや登山ブームに乗って
②森の中のサイクリングコース・・エコな、自転車の楽しさを多くの人に
③木々のチャレンジ・・自然を残し、ツリーハウスやハンモックで癒し
④音の力に注目した里山ブランディング・・鳥や虫の自然の音、
ハウスでの演奏会の音、ビアガーデンで地域交流
⑤サバイバルゲーム・・森の野戦、セミナー未開発広場の利用
⑥自然を活かした緑地の観光スポット化・・スピリチュアルスポット滝から
手打ちそば体験
⑦めぐみのホタル・・ホタルや緑地の生態系保護から環境教育
⑧癒しを求めた八王子セミナーハウス・・近隣とのふれあい、大人、子供、
森のお絵かきコース
⑨環境教育を体験する遊び場・・遊んで学べるフィールドアスレチック
⑩古くて新しい妊婦生活(世代を超えて愛されるセミナーハウス)・・妊婦の
交流と健康の促進
⑪トイカメラ貸し出しによる自然体験・・流行のトイカメラで自然体験研修
と11通りの提案がなされた。
担当の永見先生はデザインの扱う領域は、従来は「モノ」が中心でしたが
現在は「モノ」を使う「シーン」の提案から「サービス」まで領域が広がっており、
3年生の前期授業デザインシステム演習1の課題として
八王子セミナーハウスと隣地の柚木めぐみ野緑地の利用計画をテーマに設定し、
これまで学んできたプロダクトデザインや環境デザインの視点を応用展開すること、
具体的な場所での一連のデザインワークを体験することを狙いとした為との事です。
他の大学でも同様な研究をしていられるようでしたら、
学生の交流も兼ねて連携して一緒に学べると良いのですが、声を掛けてください。
Posted by コーディネーターズ at
13:41
│Comments(0)
八王子事典の巻 その3 城山中学校編
2010年06月12日

八王子市立城山中学校
鈴木さん(城山中学校校長)
2010年5月19日
―八王子事典をネット上に作るにあたって、大学や高専の研究室を
中学生に取材していただけないでしょうか。
とくに今回は東京高専なんですが、
ロボット大会に出場したロボットや、校庭を歩きまわっているヤギなど、
中学生が興味を持ちそうな研究がたくさんあります―
鈴木先生「大学や高専の研究室を中学生が取材するというのは、
基本的に面白いと思います。
うちの中学校でも、生徒の職場体験というのがあって、
中学生3年生が、取材を含めた体験をしています。
ただ、中学生に、研究室を取材する力量があるかどうか、不安です」
―その点では、「取材の講義」をしてくださる先生方がいます。
中学生に記事の書き方や写真の撮り方などを教えてくれるはずです―
鈴木先生「取材の講義も取材も夏休み中がいいですね」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
南大阪地域大学コンソーシアムの巻
2010年06月03日

多摩永山情報教育センター
第2回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナー第3分科会 「大学連携」
2010年3月15日・16日
―3月の半ばの二日間、永山の研修センターで
八王子未来学ニューFD/SDセミナーが開かれました。
泊りがけで、いろいろな分科会に分かれて討議が行われましたが、
その中の南大阪コンソーシアムのコーディネーター難波さん(写真)の講演から、
南大阪地域大学コンソーシアムがうまくいっている理由について、
まとめさせていただきました。
難波さんは、有限会社ダブル・ワークスの代表取締役で、
南大阪地域大学コンソーシアム統括コーディネーターです。
2001年に大学や学会を知的にサポートする
大学発ベンチャー・ダブルワークスを設立され、
今では大学と地域をつなぐコーディネーターの役割が中心になっているそうです―
■1■うまくいっている理由
●理由1 事務局運営を企業に委託
この会社は、大学や学会のサポートすることを目的に設立されたベンチャーです。
当時は、全国初の女子大発ベンチャーとして注目されました。
ふつう、大学コンソーシアムは大学の事務局が運営しますが、
南大阪では、大学関連の「企業」に事務局運営を委託しています。
このような事例は他にはあまりありません。
この企業が、様々な事業運営の中心的役割を果たしており、
委員会の運営、事業実践のほか、産官学地域連携で重要なコーディネータの役割や、
国や自治体の補助金や公募事業に対して申請書類を作成したり、
事務処理を行っています。
事務局には、委託企業のほかに専任職員がおり、
大学と連携しながら一体となった運営を行っています。
企業が行うことで、特定の大学に与することなく、
こういった仕事に長期にわたって継続的に責任を持ち続けられる利点があります。
(学生は数年経てばいなくなるし、大学や市の職員は自分の仕事に追われています)
●理由2 窓口の1本化
この地域の大学に対する依頼の受付として、窓口を
大学コンソーシアムで一本化しています。
言い方を変えれば地域の「ヨロズ相談所」です。
●理由3 研究者データベースあり
地域の大学の研究者データベースがあり、大学の先生の名前と
研究内容が検索できます。
これは、小さな大学でも地域貢献に参加できる可能性を広げるということを意味します。
小さくても大学の外との窓口ができ、産学官地域連携の
促進につながる、ということです。
ただ、知の連携のテーマは難しいですよ。
●理由4 学生主体で使い勝手よく
南大阪のコンソーシアムは、学生が主体です。
学生がチームの大切さを学びながら、企業と真剣勝負する場でもあります。
それは、企業からの依頼の案件で、そのおカネを学生に支払っているからです。
企業も、おカネを出している以上、100点でないとOKを出しませんから、
学生も真剣になります。
取組みによって支払われる金額は変わりますが、例えば、
ブレーンストーミングなどへの参加は2時間で5千円です。
成果は卒論に使ってもいいという方針も奏功しています。
そういった真剣さが、学生国際ショートムービー映画祭商談会オークションで、
企業が学生を落札する、という結果にも結びついています
このようにすべての事業を学生中心に行っていて、結果的にですが、
「人づくり」にもなっていました。大学からの期待が大きい部分です。
こういった育て方が、うちのコンソーシアムと組む事業を
増やしているという側面もあります。
●理由5 受託収入を高確率で獲得
収入の内訳は、(自治体、経産省や文科省などからの)受託収入が9割です。
残りの10%は、各事業会社負担、コンソーシアムの事業収入、
会員収入、となっています。
背景には、現在までのところ自治体や国などの事業を高確率で受託できている、
という事情があります。
でも、事務局運営をどう充実させ、安定した運営費をどうねん出するかは、
大きな課題です。
―また「うまくいっている理由」以外にも、
難波さんはいくつもの重要なことをおっしゃっていましたが、
その中から、「コンソーシアムの副産物」や「連携を円滑に進める方法」
「大学連携とコンソーシアムの違い」などについても、
箇条書になりますが、お伝えします―
■2■効果と副産物
●知的資源の共有
ひとつのプロジェクトに各大学の学生を集めることで、知的資源を共有できる。
●窓口一本化の効果
小さな文系大学の先生にも、コンソーシアムを通じて研究費を渡せる。
●異文化交流
学生同士の交流促進で相互に刺激あうことができる。
●授業への効果
コンソーシアムで育んだ知的資源(各種講座、効果測定、ユニークな
人材育成プログラム等)を大学の科目に還元することでができる。
■3■温度差のある大学同士を連携させて円滑に進める方法
以下のように、大学連携が大学にもたらすものを明確にして説得する
●デメリット
・競争相手とやらなくても、一人でやる方が簡単。
・他の大学とは文化が違う。
・他の大学(の先生や事務は)何を考えているか分からない
・連絡が大変。
●メリット
・10大学でやれば1/10のコストで済むので効率的。
・一人でやるより大勢でやった方が、スケールメリットがある。
・異文化交流あり。
・全体であたることが必要な共通の課題と、
各人があたれば済む固有の課題を区別することができる。
・社会的信用が増す。
■4■大学連携とコンソーシアムの違い
―現在、八王子が目指している連携には、学学連携や産学(官)連携があって、
大学のシーズと地元のニーズを結びつける、という産学連携も
八王子未来学に課されていましたが、
八王子未来学や大学コンソーシアム八王子が目指している
連携のメインは、学学連携です。
しかしその学学連携の中での「大学連携」と「大学コンソーシアム」を、
明確に区別したことはなかったように思います。その点について、
難波さんは整理してくださっています―
●大学連携
・大学に内在している。
・分担したり、合理化することで「引き算、掛け算」の発想になる。
・地域の知の拠点の確立を目指す。
・経営の効率化の実現を目指す。
●大学コンソーシアム
・大学に外在している。
・大学の人材や研究をつなぎ合わせる「足し算」の発想。
・地域の学術機能の向上。
・産学官、地域の連携推進を目指す。
●大学とコンソーシアム事業のそれぞれの特色
・アカデミックな大学⇔社会との接点を演出するコンソーシアム
■5■なぜ大学コンソーシアムが必要か(結果としてということでもある)
―そのうえで、なぜ、大学コンソーシアムが必要なのか、を難波さんは問うています―
・大学に対する社会の期待が大きくなった。
・社会が多様化。複雑化する中、ひとつの大学でできることが限られてきた。
・大学単体での体力が相対的に弱体化。→経営効率化SD
―いかがでしょう、難波さんの6倍速の講義についていくのは大変で、
とても内容の濃い講演だったのですが、今回はその一部を紹介させていただきました。
整理してみて、その重要性に気付いた次第です―
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
家政学院大学の食材の研究の巻
2010年06月02日
東京家政学院大学
(向かって右から)小口さん(家政学院大学准教授)、山﨑さん(家政学院大学講師)、
Aさん(某製薬会社)
2010年5月11日
ある製薬会社のAさんが、食材開発について
どんなことを行っていらっしゃるかを尋ねに
東京家政学院大学にやってきたところをご一緒させていただきました。
両先生を紹介してくださったのは、いつものように白井先生でした。
■小口先生
「現在は各地域の新しい食材を使って、新食感などを研究していいます。
おもに、利用しにくいものをどう再利用し、
新しい食材として使うか、といったことです。
米など、いろいろな素材を活用しようとしています。
企業との共同の研究もしておりますが、
研究の結果、家庭で作る食事としてはいいものができても、
大量生産、大量輸送の必要な企業から見る評価は異なる、ということがありました。
でも企業の評価に、大学としてはふりまわされてもいけないでしょう。
また別の成果として、学生の発想にはすばらしいものがあると思いました」
■山﨑先生
「現在の私が行っている研究の中心は、「食用花」から抽出した成分による
新機能性の探索や自然界からの有用微生物の分離・活用です。
また企業との連携では、コンセプトをお聞きし、
その内容を学生自身が消化して、進めています。
その中で、新商品のコンセプトも学生が設定し、新しい物が出来上がりました。
こちらでもやはり、学生の発想の豊かさには驚かされています」
■Aさん
「いろいろな健康食品を開発してきた人が関連会社にいます。
本日、教えて頂いたことを伝えたいと思います」
■小口先生と山﨑先生
「授業展開では現在、2つの企業に絞って行っています。
授業とは別に、各教員、数社と共同研究を進めていますが、
あくまでも教育を軸として、企業の方々の請負ではなく、
学生さんに学びの場となるかを根底に連携は進めていますので、
お話をいただいても、恐縮ですが、必ず連携できるというわけではありません」
<このブログは八王子未来がコーディネーターがおおくりしています>
Posted by コーディネーターズ at
18:03
│Comments(0)