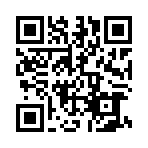オリンパスわくわく科学教室 de 東京高専サイエンスフェスタ
2010年09月24日

東京高専 de サイエンスフェスタ 八王子未来学ブース
2010年8月21日(土)、22日(日)
今年も「東京高専でサイエンスフェスタ」が行われました。
昨年は豚インフルエンザの影響で二日目が中止になりましたが、
今回は無事取り行われました。
3回目の今年は、来場者数も2千400人となり、地域に根差してきた感があります。
その「東京高専 de サイエンスフェスタ」の「八王子未来学」ブースで、
下記の4つの演目が行われました。
●「立体映像や光の不思議な現象」(オリンパス)
立体豚や人工虹、偏光現象などの催し物
●「ロボットと話そう」
創価女子短大のお姉さんたちとNECパペロ
●「考えて動くロボット」
高尾1号のデモンストレーション
●「純心大学シアター」
純心女子大のお姉さんたちによる人形劇
そう、今年はオリンパスの皆さんが参加してくたのです。
昨年、城山中学で行われたオリンパスのわくわく科学教室で
面識をいただいた黒沢さんが中心になっている完全ボランティアの「移動教室」。
この日は、槌田さんと中村さんが来てくださいました。
二人とも部長だったり、チーフエンジニアだったりのオリンパスの重要人物です。
この日は、これとは別に城山中学の皆さんが来てくださって、
そちらに回っていたので、私は下の豚の写真しか撮れませんでした
(上の写真は東京高専さんからいただきました)。
う~ん、これも昨年から続く豚の因縁なのか。
せっかく来ていただいたのに、
お二人の写真も撮れずに、豚の写真を撮っただけだとは。
ブロガーとしてとても残念です。
輸入品に押されている日本と世界の医療機器市場で、
オリンパスの製品が売れ続けることをお祈りいたします。
ちなみにこの豚、本物は黒い鍋の中にある豚人形の(虚像ではなく)実像です。
でも、たしか、レンズで見る実像ってスクリーンを立てて見たように思うし、
スクリーンも立てずに見る実像の豚が、こんなにはっきり見えるのは…分かりません。
光を豚に当てると、光が鍋の中に入って、光った豚がちゃんと現れている。
もし、この「直射日光に鏡をさらすな」と警告してある黒い鍋を大きくして、
中に等身大の豚を入れると、目の前に等身大の豚が現れるんでしょうか。
そいつが、もし少し動いたりすると、不気味でしょうね。
でも不気味な等身大の幻の豚を目の前でつかみ損ねたら、
少年少女は皆、理科系に、それも光学系に進むんじゃないかしら。。。
ただ、高さ3センチの豚を1mにすると、
鍋の直径も30センチから10mになるでしょうから、
ちょっとね~。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
八王子テレメディア・プロデューサーの巻
2010年09月23日
八王子テレメディア
遠藤さん(プロデューサー)
2010年8月16日
昨年度お世話になり、今年度も八王子未来学の
テレビ番組制作をお願いすることになった
八王子テレメディアの遠藤さんに、
プロデューサーの仕事などについて、伺いに行きました。
(写真は昨年度の撮影風景です)
――プロデューサーという仕事は何をするんですか?
遠藤さん「基本は、外部に企画を提案することです。
持ち込み企画も含めて、そういう「動き」をすばやくキャッチして、
ニーズ、予算、納期を合わせてコンセプトとしてまとめる。
しかもなるほど、という形にして話をまとめるのが大切です」
――ディレクターと呼ばれる人と、どう違うんですか?
遠藤さん「固まったコンセプトをもとに、実際に進めるのがディレクターです。
ディレクターが決まると、今度はそのディレクターと二人で、
実際にどんな番組にするかを考え、それまでの骨格に肉付けしていきます」
(詳しい内容や番組作りのプロセスは、後日インタビュー記事でお届けします)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
中学生のためのカメラ教室の巻
2010年09月22日
城山中学校
鈴木くん、城定くん、佐々木くん、鈴木校長先生、
千種さん(東京工科大学准教授)、大島哲二さん(カメラマン)
2010年7月16日
八王子事典(仮)に載せる記事を、中学生に取材してもらうために、
工科大の千種先生に、城山中学に乗り込んで、
「取材スクール」を開いていただきました。
心配そうに見ている鈴木校長先生、
そして写真には写っていませんが副校長や理科の先生に
生徒を集めていただきました。
千種先生が呼んだ、プロのカメラマンの大島さんも登場、
「目から鱗」の授業が行われたのであります。
中学生も含めて皆さんお忙しい中、大変だったはすですが、
内容はすばらしいものでした。
たとえば、下の写真2枚は、同じ段ボール箱を撮ったものですが、
近くから撮る場合と、遠くからズームを使って大きくして撮る場合で、
奥行きの方向の距離感がこんなに違うんですね。
今回は、文章の書き方ではなく、デジカメ写真の撮り方講座でしたが
千種先生が、プロジェクターと紙の資料で、
このようなズームを使った距離感の出し方や、
フラッシュのオンオフ方法、被写体以外に焦点を当ててからずらすぼかし方、
動くものをデジカメで撮る場合は少し先回りしてシャッターを押すことなど、
多彩で役に立つノウハウをいくつも教えていただけました。
また大島さんには、光の当て方で人の顔の深みや表情が全然違うこと、
撮る角度で被写体の雰囲気がガラッと変わることなど、
人物写真のプロのノウハウを直接教えていただきました。
はっきりいってこの授業、すごく役に立ちます。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
未来スクールはちおうじ第三回の巻
2010年09月12日
第三回「未来スクールはちおうじ」
学園都市センター12階セミナールーム
2010年8月14日
猛暑の中、「夏休みの自由研究を、大学の先生がお手伝い」という触れ込みで、
40組80名ほどの親子が集まりました。
午前と午後の2回に分かれ、
①「キッチンでできる化学実験」(薬科大 渡辺先生、成井先生)
②「まわしてみよう! ギリギリガリガリ」(拓殖大 渡辺先生)
③「しゃくとり虫型ミニロボットを作ろう!」(拓殖大 森先生)
④「透けて見える、小さな命。ミジンコの顕微鏡観察」(薬科大 高橋先生)
の4つが行われました。
①の「キッチン~」は、昔リトマス試験紙でやった酸性、
アルカリ性のチェックが、グレープジュースの色の変化でも、
できてしまうというもの。
(私たちのお腹の中の酸性度も、もしかしたら分かる?)
②の「ギリギリガリガリ」は、木をガリガリこする振動が伝わって、
木の先につけたプロペラを回す回転運動に変わるというもの。
③の「りゃくとり虫型ロボット」は、筋肉の働きをするバイオメタルを
取りつけて電気を流すと、くの字型の「ロボット」がたしかに歩きだしました。
④の「ミジンコ」は、顕微鏡でミジンコの心臓を見て、アルコールを入れる前後の
鼓動をカウント。酔っ払って拍数の増えたミジンコの様子を、
体を透かして確認する感じでした。
子どもたちは一様に「楽しかった」と言ってくれました。
親ごさんも楽しそうでした。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
テクニカル・カンファレンス第二回の巻
2010年09月09日
八王子未来学テクニカルカンファレンス第二回
八王子先端技術センター 開発・交流プラザ
高橋さん(拓殖大学副学長)、杉林さん(拓殖大学教授)、
前山さん(拓殖大学准教授)、香川さん(拓殖大学准教授)、
山口さん(明星大学教授)、
伊藤さん(東京高専准教授)、向川さん(東京高専技術職員)
2010年7月30日
今回のテクニカルカンファレンスには、企業も20社以上が参加していました。
拓殖大学の前山先生は、電波測定をテーマに発表されていました。
携帯電話の、ワンセグやオサイフケータイのような機能ごとの
電波測定法についてでした。電波無響室などの施設があるそうです。
同じく拓殖大の香川先生は、二足歩行ロボットの足についている複数の
「コントロール」について話されました。
産学連携の研究では、企業から持ち込まれるあいまいな質問にも答えつつ、
そのアイデアの試作品を作るようなこともされているそうです。
同じく拓殖大学の杉林先生は、新しいダイカスト金型について、
またスポット溶接についてお話されていました。
拓殖大学の産学連携研究センターはこちらのようです。
明星大学の山口先生は、昨年できた「連携研究センター」の
機能についての説明をされていました。
先生ご自身は、極低温測定、強誘電性、超伝導、熱伝導の研究をされているそうです。
東京高専の伊藤先生は
企業からの研究には段階があって、①依頼分析 ②技術相談 ③技術協力
④受託研究 ⑤共同研究 の順に進めばお互いに信頼を得られる。
いきなり共同研究をやるより、まずは、技術相談や依頼分析でお越しください、
と出席した企業の皆さんに話していました。
同じく高専の向川さんは、企業からの受託試験をして分析結果を出す際に、
ランニングコスト程度はもらうが、
基本的には非常に安くやっているので、気楽に持ち込んでほしい。
その結果を受けて、共同研究や受託研究に話を進められればいいのでは、
と話していました。
ちなみに東京高専の産業技術センターはこちらです。
この日は、ほとんど質問のなかった企業の皆さんも、
その後日をあらためて、先生にアクセスしていたようです。
うっかり質問はできませんよね。限界を見せることになるし、
やりたいネタもばれてしまう。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>