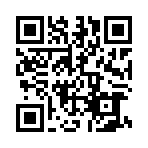南陽台地域福祉センターの巻
2010年07月25日
南陽台地域福祉センター
渡邉さん(理事長)
2010年6月17日
南陽台福祉センターの渡邉理事長をお尋ねしました。
「ロボット治験・社会福祉モニター」の試みについて伺うためです。
渡邉さんは、らいふねっとMOE理事長の菅原さんに紹介していただきました。
■介護保険の制度の使い勝手
――八王子の様々な施設でロボットの実験をする、ということは可能でしょうか。
渡邉さん「たとえば、車椅子に乗ったまま、
階段を上り下りできる「車椅子ロボット」があります。
バッテリーを積んでいて重いんですが、一段一段降りていく。
ただ、万一のときのために、うしろから支えます。
それは、うちも使いたいんです。
デイサービスは送迎があり、玄関などでの上り下りが大変だからです。
でも「壁」があります。レンタルで利用することができない、ということです。
介護保険では、利用者本人の申請でないと、レンタルできないのです。
そしてその装置は、その人のみに使えることになる。
となると、1台を複数の人に利用してもらう福祉施設では、難しい。
レンタルができないとなると購入しかありませんが、買えば1台百数十万円します。
高額である一方、車椅子ロボットは、
たとえばMOEと南陽台で1台あればいいくらいです。
この車椅子と同じことが、ロボットでも起こりかねない。
たとえば人が装着するタイプのロボットは、衰えた筋力をカバーするのが目的ですが、
それも利用者の申請で利用者だけが使うということになれば、
施設側では使いづらいでしょう。
ロボットなどの実証実験では、そういう点を考慮できるでしょうから、
複数の利用者で使えていいと思います。
要するに介護保険に問題があるんです。
このちぐはぐな制度を変えてほしいんですが、
それには政治の力が必要になってきます」
■超高齢化社会に備えて
「パぺロのようなロボットの実験なら、うちの施設でも可能です。
というのは、2015年~2020年の地域の福祉のあり方に、
私たちはとても興味があります。5年、10年後どうなっているか。
確実に超高齢者社会になるからです。
この南陽台は、高齢化率40.5%。
今は65歳以上の10%がなんらかの介護が必要なんですが、
9割のお年寄りは元気です。このあたりは、「ぴんぴんころり」が多い(笑)。
どうしてそうなっているのかを検証する必要がありますが、
見ていると、どうも、9割の人は、元気な時代に何かをやっているらしい。
それを楽しみとして続けている人が「ぴんぴんころり」。
フィンランドがそういう傾向が強い。
フィンランドでは、5、6件をまとめてグループとし、
それ全体を取りまとめて福祉が成っている。
ふつうの民間が、5、6件のネットワークを組んで、その中に、
アクティビティ(軽度の運動や遊び、趣味など、心身活性化のための手助け活動)や
癒し系のロボットが入る形のようです。
9月にフィンランドに、介護などの要員を派遣し、見学をしてきます。
理事会で承認されましたから
(南陽台地域福祉センターの理事会には8人の理事がいて、渡邉さんがその理事長)」
■ロボット治験 パペロ
「一人に1台使える装置というのではなく、共通で使えるものがやりやすい。
広く「治験」を利用するのは、必要でしょう。
南陽台は、40人の職員がいますし、パぺロなら、
広間に1台置いて使ってみるという使い方になります。
■盲導犬型ロボット
現在、この施設でサービスをしている範囲では、目の不自由な方はいません。
耳が先天的に不自由な方はいますが。
ただ、介護と医療の両方をやっていて、私たち介護事業者が
頼りにしている病院が近くにありますから、
そういった病院や盲学校がいいかもしれません。
<このブログは八王子未来学がおおくりしています>
八王子事典の巻 その5
2010年07月24日
八王子事典第一回編集専門委員会(東京高専)
奥の左から、望月さん(創価大准教授)、森さん(創価大教授)、
釜谷さん(工学院大准教授)、数馬さん(工学院大教授)、榎本さん(工学院大教授)、
岡戸さん(コンソーシアム)、設楽さん(コンソーシアム)、千種さん(工科大准教授)、
岩清水さん(東京高専、見えてないけど)、浅野さん(東京高専准教授)
2010年6月11日
「八王子事典(仮)」の第1回編集専門委員会が開かれました。
人気の学園都市センターは予約できず、場所は東京高専の多目的室です。
今回は第一回ということもあって、
まずは意見を出し合ってみる場でもあったかもしれません。
■査読
論文の世界には「査読」というものがあるそうです。
査読を受けたものが論文として認められる、みたいな。
「編集専門委員会に査読の機能を持たせましょう」
「査読は専門性が必要ですから、
ここに出席している先生だけでは、範囲の広い「八王子事典」は荷が重いのでは?」
「協力委員や、コンソーシアムを通じて八王子の23大学を紹介してもらい
役割分担をすればいいかも」
「査読して審査するところは、権威が必要でしょう」
■ユーザ
「まず小中学生(背伸びをした小学生と、中学生)がターゲット」
「とっかかりは、「歴史」と「風俗習慣(ファンキーモンキーベイビーズとか)」」
「若い人に使ってもらいましょう」
「中学生の夏休みの宿題で、たとえば産業→桑や絹織物、みたいに使えれば」
■コンテンツ
「先生の執筆とともに市民からの投稿を募集しましょう」
「教員が書くページ、訓練された人が書くページ、ブログ、の3つの分野があるかも」
「情報量が多いので、記事より写真がいいのでは?」
「写真を見せて、どこだかわかるか?というクイズもいい」
「八王子学でフォトコンテストをやりました。
テーマを与えて募集したところ、まだ数はそれほどではありませんが、
いい写真が集まりましたよ」
■協力委員は?
「八王子学会や八王子の桜を守る会といった市民の会に協力を
お願いするのはどうでしょう」
■当面の項目選び
「A先生、千人同心やその周辺+スポーツ、
B先生、生物中心、動植物、
C先生、日本史20項目、
D先生、産業の一部なら。
E先生、校内から先生を紹介、
F先生、ま、こんな感じで、とりあえず項目案を出してみましょう」
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
電通大の産学連携の巻
2010年07月23日
「産学官連携DAY in 電通大」
電気通信大学
2010年6月2日
調布にある電通大で、「産学官連携DAY in 電通大」という
産学連携イベントがありました。
企業から研究テーマが持ち込まれるのを待つだけでなく
積極的に研究室を公開していくためのイベントだということです。
上の写真は、学生のアイデアを紹介する発表会で、
大勢の企業関係者が押しかけている、といった感じでした
(個人的には、甲羅の上に植物を配置して、水を自動でさして育てる
カメロボット<植物と動物の中間を狙ったとか>が、
面白いと思いました。他にもキーが4つしかない日本語入力装置や
非難の言葉がどんな痛みを引き起こすかを感じるシステム、
などなどいろいろな提案が出ていました。
いい審査結果が出て研究費が出るといいですね)。
とても盛り上がっていましたし、高専などと比べて、
その規模の大きさと層の厚さに、当然なんでしょうが、驚きました。
ここに誘ってくださったのは、
先日のコーディネーター情報交換会に出席し、
「電通大の得意分野はITです。ITの連携はどうぞ電通大へ」とおっしゃっていた
電通大産学官連携センター特任教授・河野さんです。
産学連携を模索していらっしゃる皆さん、
電通大の今回、6回目というこのイベントに
一度行かれるといいと思いました。
京都や南大阪に行かなくても、面白いものは意外と地元にありそうな。。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
コーディネータ情報交換会の巻
2010年07月01日
八王子先端技術センター開発・交流プラザ会議室
八王子市産業振興部・大西主幹、八王子市産業政策課・柏田主査、
八王子市産業政策課・奈良主任、
JST産学連携展開部・田中主査、都産技研・瀧山産学公連携コーディネーター、
中小企業振興公社多摩支社・和田統括コーディネーター、
八王子先端技術センター・川崎相談員、同・沖川相談員、
TAMA協会・竹内事務局次長、TAMA協会・小林マネージャー、
サイバーシルクロード・土方サブリーダー、(同・高橋事務局次長)、
首都大学東京産学公連携センター・宗木コーディネーター
TAMA-TLO・松永事業部長、農工大TLO・大平アドバイザー、
電通大産学官連携センター・河野特任教授、
TAMA-TLO・武田コーディネーター、大学コンソーシアム・竹中主任、
八王子未来学コーディネーター・大久保、斎藤、出口
2010年5月20日
平成12年度の企業支援総合コーディネート事業は、八王子市が
「地域企業のためのワンストップ相談所」を目指しているプロジェクトのようです。
よろず相談所ですね。南大阪地域コンソーシアムと違うのは、
大学が中心にあるわけではない、ということだと思います。
(大学関係では、首都大学東京、電通大、農工大、そして高専が参加していますが)
まず、文科省のJST産学連携展開部の田中さんから、
22年度の補助金の数々が説明されました。
それを皮切りに、様々な意見交換がされましたが、
白熱したのは、産業と大学、つまり産学コーディネートのやり方と、
そのコーディネーターがこの場で何を話し合うべきか、ということでした。
・先端の技術から、派生していろいろな技術が生まれるので、先端技術を話してもらう。
・いや、10年後の先端の手前の1~3年の技術が、企業には必要なのだ。
・(専門を深く掘り下げる)I字型もいいが、それだけではだめで、
(幅を持った)V字型の知識が必要だ。
・大学の先生は、先端の深さをさらに掘ったところをやる。
だから、1~3年先を見ている企業とは、もともと合わない。
・先端よりむしろ、少し古いくらいの技術の方が、企業に受け入れられる。
・コーディネーターの出身母体が、何が得意なのかを言うべき。そうすれば、
この案件は、得意なあのコーディネーターの投げてみよう、と考えることができる。
今回、電通大が、ITが得意だと言ってくれたのはとてもいい。
・いや、得意分野ではない、切り捨てられる他の分野にも光るものがたくさんある。
だから得意分野を言うのが必ずしもいいわけではない。
・コーディネーターが、信頼されて、やっと企業に本音を言ってもらえる
(企業はニーズを含めた本音を言わない)。
この場では、公にはできないことでも、コーディネーター間の
情報を持ち寄って、相談するのがいい。
知識と知識の交換ならまだいいですが、そこに秘密情報も絡んでくると、
なかなか難しいですね。
たとえば結婚情報も、自分についての教えたい情報と、
教えたくない情報があり、お互いのそれを全部知っている仲人がいたら、それは神様でしょう。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
Posted by コーディネーターズ at
23:18
│Comments(0)