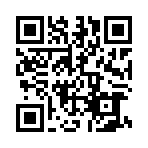探検部が目指す「もう一つの箱根駅伝」の巻
2010年01月29日
もうひとつの箱根駅伝
齊藤さん(女性)、栗原さん
09年12月3日
今回は、各大学の探検部が企画した
「もうひとつの箱根駅伝」のご紹介です。
右側の栗原さんは、東洋大学文学部3年、東洋大探検部の主将。
左側の齊藤さんは、拓殖大学国際学部2年、拓殖大探検部隊員で、
「もうひとつのプロジェクト」の会計を務めているそうです。
この、めずらしい探検部隊員の撮影に成功したのは、
拓大の学園祭で、探検部の皆さんのお話を伺ったのがきっかけです。
---
■探検部って何をするんですか?
「私は中国の広州に一人で行きました。
天台宗の総本山に、拓殖大の国際学部の友達の家を
渡ったりして行きました(齊藤さん)」
栗原さん「トゥクトゥク(起動音がトゥクトゥクというバイク。
東南アジアに多い)で、
タイ文明が栄えたところを北から南へ歩いた人とかもいます(栗原さん)。
そうゆうことをやるひとが集まるのが探検部ですが、
関東学生探検連盟
に加盟している部が多いです」
■その探検部が行う「もうひとつの箱根駅伝」とは何ですか?
「「もうひとつの箱根駅伝」は、「もうひとつのプロジェクト」のひとつで、3つの大きなものがあります。
①富士山清掃
②箱根駅伝の清掃
③100kmマラソン
100kmマラソンは、高尾山とビッグサイトの間を
ゴミ拾って走るマラソンで、(昨年の)8月の29日と30日に
すでに挙行されました。ゴミを拾いながら、だらだら走る感じで、
参加者は60名。
スタッフも40名いて、車で移動してゴミを受け取ったりします。
(飛行士は3人だけど、それを支える地上スタッフが
たくさんいるアポロ計画みたいな)
参加者は「ちょうど自分の大学での研究対象だったから」とか
「仲のいい友達の人がやっているから」という理由の人もいて、
探検部以外の人もずいぶんいます。
昨年(2009年)は14大学17チーム出場しました。
12/3現在で80~90人くらいが出場予定です。
それに応援(お祭り)が好きだといって「参加」する人もいる。
応援する人を見て、なんだろうと思った人によってこの活動が
広まるので、応援(だけ)する人もありがたいです。私たち実行委員は、
ボランティアで活動する人に、いい気持ちに
なってもらうために準備をします」
■プロジェクトの目的は何ですか?
「世界を1mm動かすことです。
ボランティアスピリットや人との交流を広めたい。感じてほしい。
それに馬鹿なことをしないと学生が集まってくれないということもあります。
最初から参加してくれている人もありがたいですが、ふつうは来てくれない
ような人に見せたい。「こういうことをやっている」と思ってもらえれば」
■でも探検部がまたなぜゴミ拾いをするんです?
「自然環境が変わると探検部としても困るんです。
山を登っていても、ゴミがひどい。だから富士山清掃、
となったわけです。自分が行ったスリランカはとてもひどい。
瓶とか缶とか捨てれば自然に帰ると思っているかもしれない」
■探検部の合宿はどんな感じですか?
「もし何も食べるものがなくても、生きていける、生きていくための
技術をつかむために無理やり合宿しています。根性がある人ばかりでなく、
最初は強くなくても、探検部に入るとすごく強くなる。
この前、ふつうの学生の中でもシャイだった女の子が、
「一人で山で野宿してしまいました」みたいに言ってました。
合宿や探検は計画を立てて、スケジュールを組み、
緊急連絡の体制図を提示して、大学に報告します。
東洋大の主将として審議して、安全なものしか通しません。
ちょっとでも甘いところがあったら通さない。
そんな探検部は仲間意識が強く、家族みたいですね。
ご想像に反して、女子が多いですよ。拓殖大は30人中6人が女子、
東洋大は4割方女子です。
男だけの探検部を持つ大学もいくつかあります」
■合宿では何をするんですか?
「地図の見方、懸垂下降とかを全員がこなします。
懸垂下降で手袋をするかどうかは好みですが」
■なぜ探検部に?
「べつに探検したかったわけではなく、
探検部の看板に惹かれて行ってみたら、すごく内面的に
おもしろい人ばかりだったので、自分もなりたいと思って(齊藤さん)。
高校でも山岳部でした。大学に入って、ワンダーフォーゲルや山岳部に
入れればいいと思っていたんですが、いくつか見て、一番フィールドが
多かった探検部を選びました。山だけではなく、沢、山、川、穴、
洞窟、無人島、海…(栗原さん)」
■抱負
「年々、未知のフィールドがなくなっています。
「もうひとつのプロジェクト」もそうですが、
探検とは何かを考えながら、新しいフィールドを探して
いきたいと思います」
----
さすがは文系。こんな「馬鹿な」ことをみんなでできるの
はすばらしい!!
私も学生時代に100kmハイクをやって死にそうになりましたが、
それをマラソンで走るというのは、まずあり得ない、というのが率直な感想です。
しかも走りながらゴミを拾う?……あり得ない。
こんな人たちが、人類の所有する価値観をひとつひとつ増やして
いってくれるんですね。
東洋大の主将が、部員の探検計画を「査定」して、
危ないものには許可を与えない、と聞くに及び、その馬鹿で真摯な探検に、
私は感動しました。感動したのに、このブログが1/9、10の
「もう一つの箱根駅伝」の開催日に間に
合わなかったことをお詫びします(こういうのも馬鹿で真摯な態度ですかね)。
<このブログは、八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
「ボランティアによろしく」をよろしく、の巻
2010年01月27日
09年12月3日
八王子ボランティアセンター
大島さん(主査)
今日は、大島さんにお願いをしにやってきました。
学生や社会人ボランティアの人が、自分で日記や自己紹介をアップするサイト
「ボランティアによろしく」のトップパッターを務めてください、
というお願いです。
この、「八王子未来学-旅の途中」は、コーディネーターが書くブログですが、
「ボランティアによろしく」は、ボランティアの方や、
私のようなボランティア未満の人に
共通のIDやPWをお伝えして、書きこんでいただければというサイトですが、
やはりなかなか難しい。
学生さんが、なかなかつかまらないというのが12月の状況でした。
伺ったメルアドも、急に使えなくなったりするし、
この3月に卒業する人も何人もいる。
大島さんがおっしゃっていましたが、
学生さんとの関係が切れてしまう、というのはよく分かりました。
それに、「ブログを書いてくれ」とお願いすることの難しさもあります。
皆さん、忙しいですからね。
大島さんには、その趣旨にすぐに賛成していただいて、
お忙しいのに、目の前で第一回のブログを書いてくださいました。
http://yoroshiku.tamaliver.jp/
何が起こるか分からない時代に入っていますし、
ボランティアの紹介や連絡が取りあえるサイトができれば、
い~な~と思った次第です。
皆さんのところに伺ったら、この「旅の途中」とともに、よろしくお願いいたします。
な~に、簡単ですよ、ブログなんて。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
八王子テレメディアのお仕事の巻 その1
2010年01月26日

八王子テレメディア
遠藤さん(右端)大久保さん(コーディネーター)、
浅野さん(東京高専准教授-現代企業論)、斎藤さん(コーディネーター)
09年12月2日
八王子未来学で、大学連携事業の様子を番組として作り、
ケーブルテレビで放映する企画が始まりました。
今日はそのための第一回会合で、八王子のケーブルテレビ局、
八王子テレメディアの放送サービス部制作課・遠藤さんとのご挨拶です。
テレビ番組を作るのは、なかなかできる経験じゃないですよね。
本を書くのも絵を描くのも、基本は一人。
一方テレビ番組は、映画ほどではないにしても、
リアルな世界の登場人物とモノと場所を、
スケジュールを組んでシナリオを元に組み合わせなくてはなりません。
接着剤は、いいコンセプト、というところでしょうか。
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
自律走行ロボット in つくばチャレンジ その2
2010年01月25日
つくばチャレンジ2009
(完全自律走行ロボットによる公道に用意されたコースの完走を目指すチャレンジ)
多羅尾さん(東京工業高等専門学校機械工学科准教授)、
山内さん(同機械工学科5年生)、江口さん(同機械工学科5年生)
2009年11月20、21日
(前回からの続き)
■トライアル(予選)突破!
高尾1号の番が来た!
来た!と言ったって、何ができるわけでもない。
うっかりロボットに触ったら失格だ!
「スタート!」っていう声が響いて、スイッチを入れて、
あとは1号の後をついていく。審判も観客もいる。
あそこの段差は要注意、うまくプログラム通り避けてくれるか?
ピコ、ピコ、ピコ、ピコ・・・・。おじさん、近づかないで!
ピコ、ピコ、ピコ、ピコ・・・・。
たまった落ち葉につっこまず、ピコピコピコピコピコ…。おーーーっ。
長―く感じたけど、ゴールイン!
なんだかんだ言いながら、初出場でトライアル突破!
ゴールしたあと、続く本走行のコースをそのまま試走。
この茂みでは右に行き過ぎ、おっとここはポイントが少しずれている…。
過去のGPSデータ(9/11)を使ったポイントの設定のし直し。
プログラムも。壁からどのくらいのところを走るか、修正しよう。
明日の本走行に向けて、筺体のカドを覆う、
めくれかかっている黄色いゴムを直して、ねじの締め直し。
スタート順は、当日に発表されるから、それまでは分からない。
(トライアルの成績。東大や名古屋大、中国の大学も来ているし、産総研、NHK、日立といった顔ぶれも)
■初日の全体の感想
同じようなメカ好きの人間が集まったという印象はある。
みんな高専の学生の雰囲気と似ている。
超有名な企業や大学が10人近いチームで参加しているところが多い中、
高専は先生を入れて3人。多羅尾先生は、当日、主催者側の仕事に回ったので、
実質二人。けな気だ。感動するね。
しかも、GPSで設定する最初の2ポイントの間を高専の敷地内で
走れるようになったのは、11月4日。それからまだ16日目で、
2週間ちょっとしかたっていない。動くようになってから数えても1ヶ月。
未来学の予算をつぎ込んだんだ、と言う浅野先生も、
その事実を聞いて「え~! そうなの?」って驚いていた。
トライアルでは、五分のスタート制限時間をいっぱいに使っても出発できない
チームや、かなり時間をかけて出発するチームが続出し、時間が押していった。
トライアルで出場66チーム中34チームが残った。
6分29秒は16番目くらいの記録。スピードを競っているわけではないけど。
去年は1kmの本走行での完走が1チーム。さて、今年は?
(下部の駆動系をはずして緊急に修理中!)
■トラブル!
本番2時間前。試運転中に突然、ガクンと急停止するようになった。
大変だ。先生も入って、緊急修理。どこが悪いんだ、分からない。
リセットするしかない、どうしよう、時間がない、
でもデータを書き留めておけば10分でデータを回復できる、
と山内くんが提案し、よしそうしよう、となって、リセット、
しかし、おー、動く、これは、直った。30分ほどで。
原因は不明、でも「たぶん、バッテリー端子のネジがゆるんでいた」。
直ったけど…上り坂のときに、おかしな音がする(江口くん)。。。でもやるしかない!
■出走
そんなこととも知らず、司会の女性がマイクで
「ゼッケンが18番、出走順も18番目、縁起がいいですね!」
山内くん「はあ…。頑張ります!」
スタートは調子よし。いつも通り、ピコピコ言いながらゲートを出る。
最初のポイントで、ちゃんと右に曲がり、直進していった。これはいけるぞ!
(この写真は未来学のサイトからいただきました)
でも、30mほど行ったところで高尾1号、立ち止まる。
ピコッ、ピコッと鳴ってはいたので、コンピュータはいつものように、
状況確認をしているのかと思ったけど、間もなくピコッも言わなくなって、
20秒たった。動かない。
「ヒューズが飛んだ」(江口くん)と言って、審判に「だめです」と告げてゲーム終了。
無念。みんな沈黙。審判も「残念だ」とつぶやいて立ち去る。
■原因
動力系のヒューズが飛んだ。
さっき解体したときも、ヒューズを確認したんだけど。。。
うーん、また今度、頑張ろう! …っていうか次の学年の連中、頼んだ!
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
自律走行ロボット in つくばチャレンジの巻 その1
2010年01月24日
つくばチャレンジ2009
(完全自律走行ロボットによる公道に用意されたコースの完走を目指すチャレンジ)
多羅尾さん(東京工業高等専門学校機械工学科准教授)、
山内さん(同機械工学科5年生)、江口さん(同機械工学科5年生)
2009年11月20、21日
■■第1日

■出発
11月20日朝、土浦市のビジネスホテルを出発。7:15am。
途中、多羅尾先生と学生の二人は、コンビニに寄って食料を調達。
筑波・つくば市の周辺は起伏のない、まっすぐな道の続く見渡す限りの平野。
東京の北にも、こんなに広くて平べったい土地があるんだ。
筑波(近辺)育ちの浅野先生によれば、もとは広大な松林だったとか。
遠くに(唯一の起伏)筑波山がある…。
8時前に、競技が開催される中央公園に到着。
今日ここで、ロボットの自律走行の公道でのチャレンジが行われる。

(東京高専から出場する高尾1号)
■高尾1号
ボディの下部の車輪やモーターの駆動系部分は既製品。
モーターは中国製らしい。
体重は60kg台後半で、重さのほとんどがバッテリー。
前面で目立っているCD板は、雨やゴミを逃れる覆いで、
丸ければ何でもよかったらしい。
身長があと数センチ高いとレギュレーションにひっかかるので、
ロボットが傘をさすわけにはいかない。
そのCDの下のレンジセンサからレーザーが出て走査、
だいたい1秒間に3回、周囲を認識する。
ツノのてっぺんには、2万km上空のGPSから信号を受け取る受信装置がついていて、
中央には、ウィンドウズメッセンジャーやヤフーメッセンジャーで使う
WEBカメラがついているけど、これはフェイクだって。
本当は画像処理に使いたかったんだけど、実装が間に合わなかった。
リモコンで動かすときは、ゲーム機のコントローラーをつなげる。
■制御の仕組み
制御については、GPS装置と、その後ろに黒くて丸く出っ張っている電子コンパスで、
広範囲な全体の中での位置と姿勢を割り出す。GPSの情報で得られるのは、
緯度と経度だけ。それを距離で表された位置情報に変換する。
レンジセンサでは前方270度の角度を認識できるできるけど、
通常は40度の範囲で見ている。
遠くから障害物を認識している場合は前もって避けようとするけど、
直前に出現した場合は後退する。
レンジセンサは2台あって、下ので前方を、上の斜めので地面を走査している。
GPS が使えないところでは車輪の回転数を割り出すエンコーダで、
現在地を把握する場合もある。
電子コンパスは、そこそこ安いものを購入。うん十万円の高いものは、
反応が速いけど、これは速い動きが苦手。
GPSも、複数の衛星の位置関係により、精度がかなり変わってくる。
真上に複数あれば、ビルの谷間でも位置が分かるけど測量の精度は落ち、
広範囲に広がっていると測量の精度は上がるけど周囲の建物や樹木に
妨害されやすくなり、いわば二律背反みたいなところがある。
それなのに、いわゆるカーナビの精度がかなりいいのはどうしてだろう。
参加している他チームの人がみんな、電子コンパスについて
「これは何?」と質問してくる。まだ珍しい。電子コンパスと
GPSの二つがこのロボットの位置と姿勢を知るためのメイン。
弱点は雨。回路に入ってしまっては困るし、水滴が付着すると
レンジセンサに影響する。夕日などの日光も影響するかもしれない。
レンジセンサは、地面の溝の認識がまだうまくできないときがある。
地面から立っている壁はOK。
それと子供など、人に進路をふさがれると、進めない。

■つくばチャレンジが始まる
ついにつくばチャレンジが始まった。筑波の空は快晴。風もない。
1番目の走者は、スタートに失敗。
スタート!って司会者(=スターター)に言われても、
まったく動かないチームも多数あるし、動き出しても、
5m進んで、公園に出るゲートにつっこんでリタイアするロボットもいくつもある。
完走するチームが出るたびに「○○チームが4分24秒で完走しました」
のように場内にアナウンスされる。時間を競っているわけじゃないのに。
二輪走行、とくにセグウェイが注目を集めていた。東北大学だったか。2番目の出発だった。
(つづく)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
(完全自律走行ロボットによる公道に用意されたコースの完走を目指すチャレンジ)
多羅尾さん(東京工業高等専門学校機械工学科准教授)、
山内さん(同機械工学科5年生)、江口さん(同機械工学科5年生)
2009年11月20、21日
■■第1日
■出発
11月20日朝、土浦市のビジネスホテルを出発。7:15am。
途中、多羅尾先生と学生の二人は、コンビニに寄って食料を調達。
筑波・つくば市の周辺は起伏のない、まっすぐな道の続く見渡す限りの平野。
東京の北にも、こんなに広くて平べったい土地があるんだ。
筑波(近辺)育ちの浅野先生によれば、もとは広大な松林だったとか。
遠くに(唯一の起伏)筑波山がある…。
8時前に、競技が開催される中央公園に到着。
今日ここで、ロボットの自律走行の公道でのチャレンジが行われる。
(東京高専から出場する高尾1号)
■高尾1号
ボディの下部の車輪やモーターの駆動系部分は既製品。
モーターは中国製らしい。
体重は60kg台後半で、重さのほとんどがバッテリー。
前面で目立っているCD板は、雨やゴミを逃れる覆いで、
丸ければ何でもよかったらしい。
身長があと数センチ高いとレギュレーションにひっかかるので、
ロボットが傘をさすわけにはいかない。
そのCDの下のレンジセンサからレーザーが出て走査、
だいたい1秒間に3回、周囲を認識する。
ツノのてっぺんには、2万km上空のGPSから信号を受け取る受信装置がついていて、
中央には、ウィンドウズメッセンジャーやヤフーメッセンジャーで使う
WEBカメラがついているけど、これはフェイクだって。
本当は画像処理に使いたかったんだけど、実装が間に合わなかった。
リモコンで動かすときは、ゲーム機のコントローラーをつなげる。
■制御の仕組み
制御については、GPS装置と、その後ろに黒くて丸く出っ張っている電子コンパスで、
広範囲な全体の中での位置と姿勢を割り出す。GPSの情報で得られるのは、
緯度と経度だけ。それを距離で表された位置情報に変換する。
レンジセンサでは前方270度の角度を認識できるできるけど、
通常は40度の範囲で見ている。
遠くから障害物を認識している場合は前もって避けようとするけど、
直前に出現した場合は後退する。
レンジセンサは2台あって、下ので前方を、上の斜めので地面を走査している。
GPS が使えないところでは車輪の回転数を割り出すエンコーダで、
現在地を把握する場合もある。
電子コンパスは、そこそこ安いものを購入。うん十万円の高いものは、
反応が速いけど、これは速い動きが苦手。
GPSも、複数の衛星の位置関係により、精度がかなり変わってくる。
真上に複数あれば、ビルの谷間でも位置が分かるけど測量の精度は落ち、
広範囲に広がっていると測量の精度は上がるけど周囲の建物や樹木に
妨害されやすくなり、いわば二律背反みたいなところがある。
それなのに、いわゆるカーナビの精度がかなりいいのはどうしてだろう。
参加している他チームの人がみんな、電子コンパスについて
「これは何?」と質問してくる。まだ珍しい。電子コンパスと
GPSの二つがこのロボットの位置と姿勢を知るためのメイン。
弱点は雨。回路に入ってしまっては困るし、水滴が付着すると
レンジセンサに影響する。夕日などの日光も影響するかもしれない。
レンジセンサは、地面の溝の認識がまだうまくできないときがある。
地面から立っている壁はOK。
それと子供など、人に進路をふさがれると、進めない。

■つくばチャレンジが始まる
ついにつくばチャレンジが始まった。筑波の空は快晴。風もない。
1番目の走者は、スタートに失敗。
スタート!って司会者(=スターター)に言われても、
まったく動かないチームも多数あるし、動き出しても、
5m進んで、公園に出るゲートにつっこんでリタイアするロボットもいくつもある。
完走するチームが出るたびに「○○チームが4分24秒で完走しました」
のように場内にアナウンスされる。時間を競っているわけじゃないのに。
二輪走行、とくにセグウェイが注目を集めていた。東北大学だったか。2番目の出発だった。
(つづく)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>