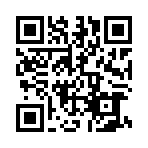南大阪地域大学コンソーシアムの巻
2010年06月03日

多摩永山情報教育センター
第2回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナー第3分科会 「大学連携」
2010年3月15日・16日
―3月の半ばの二日間、永山の研修センターで
八王子未来学ニューFD/SDセミナーが開かれました。
泊りがけで、いろいろな分科会に分かれて討議が行われましたが、
その中の南大阪コンソーシアムのコーディネーター難波さん(写真)の講演から、
南大阪地域大学コンソーシアムがうまくいっている理由について、
まとめさせていただきました。
難波さんは、有限会社ダブル・ワークスの代表取締役で、
南大阪地域大学コンソーシアム統括コーディネーターです。
2001年に大学や学会を知的にサポートする
大学発ベンチャー・ダブルワークスを設立され、
今では大学と地域をつなぐコーディネーターの役割が中心になっているそうです―
■1■うまくいっている理由
●理由1 事務局運営を企業に委託
この会社は、大学や学会のサポートすることを目的に設立されたベンチャーです。
当時は、全国初の女子大発ベンチャーとして注目されました。
ふつう、大学コンソーシアムは大学の事務局が運営しますが、
南大阪では、大学関連の「企業」に事務局運営を委託しています。
このような事例は他にはあまりありません。
この企業が、様々な事業運営の中心的役割を果たしており、
委員会の運営、事業実践のほか、産官学地域連携で重要なコーディネータの役割や、
国や自治体の補助金や公募事業に対して申請書類を作成したり、
事務処理を行っています。
事務局には、委託企業のほかに専任職員がおり、
大学と連携しながら一体となった運営を行っています。
企業が行うことで、特定の大学に与することなく、
こういった仕事に長期にわたって継続的に責任を持ち続けられる利点があります。
(学生は数年経てばいなくなるし、大学や市の職員は自分の仕事に追われています)
●理由2 窓口の1本化
この地域の大学に対する依頼の受付として、窓口を
大学コンソーシアムで一本化しています。
言い方を変えれば地域の「ヨロズ相談所」です。
●理由3 研究者データベースあり
地域の大学の研究者データベースがあり、大学の先生の名前と
研究内容が検索できます。
これは、小さな大学でも地域貢献に参加できる可能性を広げるということを意味します。
小さくても大学の外との窓口ができ、産学官地域連携の
促進につながる、ということです。
ただ、知の連携のテーマは難しいですよ。
●理由4 学生主体で使い勝手よく
南大阪のコンソーシアムは、学生が主体です。
学生がチームの大切さを学びながら、企業と真剣勝負する場でもあります。
それは、企業からの依頼の案件で、そのおカネを学生に支払っているからです。
企業も、おカネを出している以上、100点でないとOKを出しませんから、
学生も真剣になります。
取組みによって支払われる金額は変わりますが、例えば、
ブレーンストーミングなどへの参加は2時間で5千円です。
成果は卒論に使ってもいいという方針も奏功しています。
そういった真剣さが、学生国際ショートムービー映画祭商談会オークションで、
企業が学生を落札する、という結果にも結びついています
このようにすべての事業を学生中心に行っていて、結果的にですが、
「人づくり」にもなっていました。大学からの期待が大きい部分です。
こういった育て方が、うちのコンソーシアムと組む事業を
増やしているという側面もあります。
●理由5 受託収入を高確率で獲得
収入の内訳は、(自治体、経産省や文科省などからの)受託収入が9割です。
残りの10%は、各事業会社負担、コンソーシアムの事業収入、
会員収入、となっています。
背景には、現在までのところ自治体や国などの事業を高確率で受託できている、
という事情があります。
でも、事務局運営をどう充実させ、安定した運営費をどうねん出するかは、
大きな課題です。
―また「うまくいっている理由」以外にも、
難波さんはいくつもの重要なことをおっしゃっていましたが、
その中から、「コンソーシアムの副産物」や「連携を円滑に進める方法」
「大学連携とコンソーシアムの違い」などについても、
箇条書になりますが、お伝えします―
■2■効果と副産物
●知的資源の共有
ひとつのプロジェクトに各大学の学生を集めることで、知的資源を共有できる。
●窓口一本化の効果
小さな文系大学の先生にも、コンソーシアムを通じて研究費を渡せる。
●異文化交流
学生同士の交流促進で相互に刺激あうことができる。
●授業への効果
コンソーシアムで育んだ知的資源(各種講座、効果測定、ユニークな
人材育成プログラム等)を大学の科目に還元することでができる。
■3■温度差のある大学同士を連携させて円滑に進める方法
以下のように、大学連携が大学にもたらすものを明確にして説得する
●デメリット
・競争相手とやらなくても、一人でやる方が簡単。
・他の大学とは文化が違う。
・他の大学(の先生や事務は)何を考えているか分からない
・連絡が大変。
●メリット
・10大学でやれば1/10のコストで済むので効率的。
・一人でやるより大勢でやった方が、スケールメリットがある。
・異文化交流あり。
・全体であたることが必要な共通の課題と、
各人があたれば済む固有の課題を区別することができる。
・社会的信用が増す。
■4■大学連携とコンソーシアムの違い
―現在、八王子が目指している連携には、学学連携や産学(官)連携があって、
大学のシーズと地元のニーズを結びつける、という産学連携も
八王子未来学に課されていましたが、
八王子未来学や大学コンソーシアム八王子が目指している
連携のメインは、学学連携です。
しかしその学学連携の中での「大学連携」と「大学コンソーシアム」を、
明確に区別したことはなかったように思います。その点について、
難波さんは整理してくださっています―
●大学連携
・大学に内在している。
・分担したり、合理化することで「引き算、掛け算」の発想になる。
・地域の知の拠点の確立を目指す。
・経営の効率化の実現を目指す。
●大学コンソーシアム
・大学に外在している。
・大学の人材や研究をつなぎ合わせる「足し算」の発想。
・地域の学術機能の向上。
・産学官、地域の連携推進を目指す。
●大学とコンソーシアム事業のそれぞれの特色
・アカデミックな大学⇔社会との接点を演出するコンソーシアム
■5■なぜ大学コンソーシアムが必要か(結果としてということでもある)
―そのうえで、なぜ、大学コンソーシアムが必要なのか、を難波さんは問うています―
・大学に対する社会の期待が大きくなった。
・社会が多様化。複雑化する中、ひとつの大学でできることが限られてきた。
・大学単体での体力が相対的に弱体化。→経営効率化SD
―いかがでしょう、難波さんの6倍速の講義についていくのは大変で、
とても内容の濃い講演だったのですが、今回はその一部を紹介させていただきました。
整理してみて、その重要性に気付いた次第です―
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
東京高専・加藤研の研究の巻
東京家政学院大学でのロボット治験の巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
東京家政学院大学でのロボット治験の巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
Posted by コーディネーターズ at 20:54│Comments(2)
│学校・学生・就職活動
この記事へのコメント
プレゼンテーションはしっかりしてそうですね^^
Posted by ネコ好き at 2010年06月03日 21:03
ネコ好きさま
コメントありがとうございます。
難波先生のプレゼンテーションですか?
もちろん、しっかり、というか、内容の濃いプレゼンです。
スピードが早いので、聞き手が
「しっかり」しないと。
コメントありがとうございます。
難波先生のプレゼンテーションですか?
もちろん、しっかり、というか、内容の濃いプレゼンです。
スピードが早いので、聞き手が
「しっかり」しないと。
Posted by コーディネーター出口 at 2010年06月10日 19:09
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。