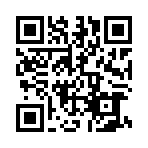自律走行ロボット in つくばチャレンジの巻 その1
2010年01月24日
つくばチャレンジ2009
(完全自律走行ロボットによる公道に用意されたコースの完走を目指すチャレンジ)
多羅尾さん(東京工業高等専門学校機械工学科准教授)、
山内さん(同機械工学科5年生)、江口さん(同機械工学科5年生)
2009年11月20、21日
■■第1日

■出発
11月20日朝、土浦市のビジネスホテルを出発。7:15am。
途中、多羅尾先生と学生の二人は、コンビニに寄って食料を調達。
筑波・つくば市の周辺は起伏のない、まっすぐな道の続く見渡す限りの平野。
東京の北にも、こんなに広くて平べったい土地があるんだ。
筑波(近辺)育ちの浅野先生によれば、もとは広大な松林だったとか。
遠くに(唯一の起伏)筑波山がある…。
8時前に、競技が開催される中央公園に到着。
今日ここで、ロボットの自律走行の公道でのチャレンジが行われる。

(東京高専から出場する高尾1号)
■高尾1号
ボディの下部の車輪やモーターの駆動系部分は既製品。
モーターは中国製らしい。
体重は60kg台後半で、重さのほとんどがバッテリー。
前面で目立っているCD板は、雨やゴミを逃れる覆いで、
丸ければ何でもよかったらしい。
身長があと数センチ高いとレギュレーションにひっかかるので、
ロボットが傘をさすわけにはいかない。
そのCDの下のレンジセンサからレーザーが出て走査、
だいたい1秒間に3回、周囲を認識する。
ツノのてっぺんには、2万km上空のGPSから信号を受け取る受信装置がついていて、
中央には、ウィンドウズメッセンジャーやヤフーメッセンジャーで使う
WEBカメラがついているけど、これはフェイクだって。
本当は画像処理に使いたかったんだけど、実装が間に合わなかった。
リモコンで動かすときは、ゲーム機のコントローラーをつなげる。
■制御の仕組み
制御については、GPS装置と、その後ろに黒くて丸く出っ張っている電子コンパスで、
広範囲な全体の中での位置と姿勢を割り出す。GPSの情報で得られるのは、
緯度と経度だけ。それを距離で表された位置情報に変換する。
レンジセンサでは前方270度の角度を認識できるできるけど、
通常は40度の範囲で見ている。
遠くから障害物を認識している場合は前もって避けようとするけど、
直前に出現した場合は後退する。
レンジセンサは2台あって、下ので前方を、上の斜めので地面を走査している。
GPS が使えないところでは車輪の回転数を割り出すエンコーダで、
現在地を把握する場合もある。
電子コンパスは、そこそこ安いものを購入。うん十万円の高いものは、
反応が速いけど、これは速い動きが苦手。
GPSも、複数の衛星の位置関係により、精度がかなり変わってくる。
真上に複数あれば、ビルの谷間でも位置が分かるけど測量の精度は落ち、
広範囲に広がっていると測量の精度は上がるけど周囲の建物や樹木に
妨害されやすくなり、いわば二律背反みたいなところがある。
それなのに、いわゆるカーナビの精度がかなりいいのはどうしてだろう。
参加している他チームの人がみんな、電子コンパスについて
「これは何?」と質問してくる。まだ珍しい。電子コンパスと
GPSの二つがこのロボットの位置と姿勢を知るためのメイン。
弱点は雨。回路に入ってしまっては困るし、水滴が付着すると
レンジセンサに影響する。夕日などの日光も影響するかもしれない。
レンジセンサは、地面の溝の認識がまだうまくできないときがある。
地面から立っている壁はOK。
それと子供など、人に進路をふさがれると、進めない。

■つくばチャレンジが始まる
ついにつくばチャレンジが始まった。筑波の空は快晴。風もない。
1番目の走者は、スタートに失敗。
スタート!って司会者(=スターター)に言われても、
まったく動かないチームも多数あるし、動き出しても、
5m進んで、公園に出るゲートにつっこんでリタイアするロボットもいくつもある。
完走するチームが出るたびに「○○チームが4分24秒で完走しました」
のように場内にアナウンスされる。時間を競っているわけじゃないのに。
二輪走行、とくにセグウェイが注目を集めていた。東北大学だったか。2番目の出発だった。
(つづく)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
(完全自律走行ロボットによる公道に用意されたコースの完走を目指すチャレンジ)
多羅尾さん(東京工業高等専門学校機械工学科准教授)、
山内さん(同機械工学科5年生)、江口さん(同機械工学科5年生)
2009年11月20、21日
■■第1日
■出発
11月20日朝、土浦市のビジネスホテルを出発。7:15am。
途中、多羅尾先生と学生の二人は、コンビニに寄って食料を調達。
筑波・つくば市の周辺は起伏のない、まっすぐな道の続く見渡す限りの平野。
東京の北にも、こんなに広くて平べったい土地があるんだ。
筑波(近辺)育ちの浅野先生によれば、もとは広大な松林だったとか。
遠くに(唯一の起伏)筑波山がある…。
8時前に、競技が開催される中央公園に到着。
今日ここで、ロボットの自律走行の公道でのチャレンジが行われる。
(東京高専から出場する高尾1号)
■高尾1号
ボディの下部の車輪やモーターの駆動系部分は既製品。
モーターは中国製らしい。
体重は60kg台後半で、重さのほとんどがバッテリー。
前面で目立っているCD板は、雨やゴミを逃れる覆いで、
丸ければ何でもよかったらしい。
身長があと数センチ高いとレギュレーションにひっかかるので、
ロボットが傘をさすわけにはいかない。
そのCDの下のレンジセンサからレーザーが出て走査、
だいたい1秒間に3回、周囲を認識する。
ツノのてっぺんには、2万km上空のGPSから信号を受け取る受信装置がついていて、
中央には、ウィンドウズメッセンジャーやヤフーメッセンジャーで使う
WEBカメラがついているけど、これはフェイクだって。
本当は画像処理に使いたかったんだけど、実装が間に合わなかった。
リモコンで動かすときは、ゲーム機のコントローラーをつなげる。
■制御の仕組み
制御については、GPS装置と、その後ろに黒くて丸く出っ張っている電子コンパスで、
広範囲な全体の中での位置と姿勢を割り出す。GPSの情報で得られるのは、
緯度と経度だけ。それを距離で表された位置情報に変換する。
レンジセンサでは前方270度の角度を認識できるできるけど、
通常は40度の範囲で見ている。
遠くから障害物を認識している場合は前もって避けようとするけど、
直前に出現した場合は後退する。
レンジセンサは2台あって、下ので前方を、上の斜めので地面を走査している。
GPS が使えないところでは車輪の回転数を割り出すエンコーダで、
現在地を把握する場合もある。
電子コンパスは、そこそこ安いものを購入。うん十万円の高いものは、
反応が速いけど、これは速い動きが苦手。
GPSも、複数の衛星の位置関係により、精度がかなり変わってくる。
真上に複数あれば、ビルの谷間でも位置が分かるけど測量の精度は落ち、
広範囲に広がっていると測量の精度は上がるけど周囲の建物や樹木に
妨害されやすくなり、いわば二律背反みたいなところがある。
それなのに、いわゆるカーナビの精度がかなりいいのはどうしてだろう。
参加している他チームの人がみんな、電子コンパスについて
「これは何?」と質問してくる。まだ珍しい。電子コンパスと
GPSの二つがこのロボットの位置と姿勢を知るためのメイン。
弱点は雨。回路に入ってしまっては困るし、水滴が付着すると
レンジセンサに影響する。夕日などの日光も影響するかもしれない。
レンジセンサは、地面の溝の認識がまだうまくできないときがある。
地面から立っている壁はOK。
それと子供など、人に進路をふさがれると、進めない。

■つくばチャレンジが始まる
ついにつくばチャレンジが始まった。筑波の空は快晴。風もない。
1番目の走者は、スタートに失敗。
スタート!って司会者(=スターター)に言われても、
まったく動かないチームも多数あるし、動き出しても、
5m進んで、公園に出るゲートにつっこんでリタイアするロボットもいくつもある。
完走するチームが出るたびに「○○チームが4分24秒で完走しました」
のように場内にアナウンスされる。時間を競っているわけじゃないのに。
二輪走行、とくにセグウェイが注目を集めていた。東北大学だったか。2番目の出発だった。
(つづく)
<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>
東京高専・加藤研の研究の巻
東京家政学院大学でのロボット治験の巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
東京家政学院大学でのロボット治験の巻
舘中学校+拓殖大学=出張ものづくり教室の巻 2010
学園祭へGO! 造形大の巻
八王子がわかる事典と中学生の巻
第3回「八王子未来学」ニューFD/SDセミナーの巻
Posted by コーディネーターズ at 15:11│Comments(0)
│学校・学生・就職活動
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。